跳び箱って何のため?現代における意味と効果とは


片山 拳心(KATAYAMA KENSHIN)
三重県松阪市のサンパーク1階で、こども運動教室to JOY(トゥージョイ)の代表を務めています。
キッズスイミングスクールやフィットネスジムでの指導経験に加え、消防士として多くの現場にも携わってきました。
現在は、消防を退職後に、科学的根拠に基づく安全で楽しい運動教室を開業。
保有資格
- 運動遊び実践サブリーダー(NPO運動保育士会)
- 子育て脳機能アドバイザー/ディレクター
- 幼児運動遊び実践アシスタント
- キッズコーディネーショントレーナー(KCT)
- (一社)スポーツリズムトレーニング協会認定
・ アドバンスドディフューザー(AD)
・ リズムステップディフューザー(DF)
「跳び箱って、今の時代にも必要なの?」
「うちの子、跳べないけど意味あるの?」
そんなふうに感じたことありませんか?
跳び箱には“跳べるかどうか”以上の大切な意味があり、
子どもの心と体の成長を支える貴重な教材として、今も運動教室で活用され続けています。
この記事では、跳び箱の教育的な価値や、苦手な子でも楽しめる工夫、そして三重県松阪市のこども運動教室to JOY(トゥージョイ)での実践例を交えながら、
「跳び箱を通じて育つ力」についてわかりやすくご紹介します。
読み終えた頃には、「うちの子にも跳び箱、やらせてみようかな」と思えるようになっているかもしれません。
著者の片山が代表を務める運動教室情報
「うちの子、運動が苦手かも…」
そんな保護者の声に応えるのが、
三重県松阪市のサンパーク1階『こども運動教室 to JOY(トゥージョイ)』です。

to JOYでは、従来の体操教室やスポーツ少年団ではなく、
こども運動教室to JOYではこどもに合った活用方法が見つかる!
- 苦手な運動が 人目を気にせずに克服できる「パーソナルレッスン」
- きょうだいや友達と一緒に受けられる「グループレッスン」
- 雨・酷暑・ 花粉が 厳しい時期でも自由に遊べる「室内公園」
 片山 拳心
片山 拳心👉 詳しくはto JOY公式ページ、公式インスタグラム、
申し込みやご質問は公式ラインでお待ちしております。
跳び箱って何のため?
「跳び箱って必要あるの?」「うちの子、全然跳べないけど意味あるの?」
そんなふうに感じたことはありませんか?
実は、跳び箱に疑問を抱くのはごく自然な感覚です。
現代では運動の多様化が進み、跳び箱よりも球技やダンスに興味を示す子も増えています。
それに加えて、跳べないことで「劣等感」や「苦手意識」が芽生えるのではないかという不安を持つ保護者も少なくありません。
けれど、跳び箱は単なる「跳べる・跳べない」の判定だけが目的ではありません。
子どもの体と心の成長をサポートするための、大切な運動のひとつ
なのです。
ここからは、跳び箱に込められた意味や教育的効果、現代でも活用され続けている理由を、
わかりやすくご紹介していきます。
跳び箱に疑問を感じるのは自然なこと
保護者の中には「跳び箱って必要?」「跳べなくても困らないのでは?」と疑問を持つ方もいます。
実際、現代の子どもたちの生活環境は昔と大きく変わりました。
公園で思いきり体を動かす時間が減り、スクリーンに向かう時間が増えたことで、
跳び箱のようなダイナミックな動きに馴染みのない子どもも少なくありません。
また、跳び箱が「跳べたか、跳べなかったか」だけで評価されるように見えると、
運動が苦手な子にとってはプレッシャーに感じてしまうこともあるでしょう。
だからこそ、跳び箱の“意味”や“役割”を知ることが大切です。
そのうえで、子ども一人ひとりに合った関わり方を考えることで、
運動への苦手意識を減らし、自信へとつなげることができます。
跳び箱は“ただ跳ぶ”だけじゃない運動
跳び箱というと、「跳べるかどうか」ばかりに注目されがちですが、
実はその動作には、さまざまな身体能力が関わっています。
助走でスピードをつけ、両手で体を支え、空中でバランスをとりながら着地する。
この一連の流れには、瞬発力・バランス感覚・空間認識・筋力・柔軟性など、全身の協調運動が必要です。
さらに、跳び箱は「チャレンジ精神」や「勇気」を育てるトレーニングでもあります。
跳ぶ前にドキドキする、挑戦するか迷う、そんな葛藤を乗り越える経験こそが、
子どもの心の成長につながるのです。



「跳び箱は、ただ跳ぶだけの運動ではありません。体の力だけでなく、“心の力”も育ててくれるんです。」
苦手意識が生まれる背景とは?
跳び箱に対して「苦手」と感じる子どもは少なくありません。
その背景には、さまざまな要因があります。
まず一つは、「失敗体験」の影響です。
跳び箱でうまく跳べなかった、勢いが足りずにつまずいた、着地で転んでしまった
こうした経験が、子どもにとっては強い印象として残り、「もうやりたくない」という気持ちに繋がってしまうのです。
また、跳び箱は“怖さ”を感じやすい種目です。
高さや助走のスピード、跳んだあとの空中動作など、普段とは異なる体の使い方に戸惑うこともあります。
さらに、周囲からの比較やプレッシャーも原因の一つです。
「みんなできているのに自分だけできない」と感じると、自信を失いやすくなります。



こうした心理的な壁に向き合うには、「できない」ことを責めず、
一歩ずつ成長を見守る姿勢が大切です。
現代でも跳び箱が使われ続ける理由
「跳び箱って、昔からあるけど、今でも必要なの?」
そう思う方もいるかもしれません。
実際、跳び箱は100年以上前から日本の体育教育に取り入れられており、
今なお多くの学校や運動教室で活用されています。
その理由は、
跳び箱が単なるスポーツ種目ではなく、子どもの運動発達を総合的に支える教材だから
です。
跳ぶという動作の中には、体をコントロールする力や、心のコントロールも含まれています。
運動が多様化した今だからこそ、こうした基礎的な全身運動はより重要になってきています。
ここでは、跳び箱が長年支持され続けてきた背景と、
現代の教育現場や運動教室で求められている理由について、具体的に解説していきます。
跳び箱で鍛えられる5つの運動能力
跳び箱は、見た目以上に多くの体の使い方を必要とする運動です。
1回跳ぶだけでも、以下のような5つの力が同時に鍛えられます。
- 瞬発力:助走から跳躍へと一気に力を伝える動作
- バランス感覚:空中で姿勢を保ち、着地を安定させる力
- 柔軟性:膝や腰を使ってしなやかに跳ぶ動き
- 筋力:腕で体を支え、脚で地面を蹴る力
- 空間認識力:タイミングや距離感をつかむ力
これらはすべて、日常のあらゆる動作の土台になります。
つまり、跳び箱は「運動の基礎力」をまんべんなく育てる総合トレーニングなのです。


達成体験が子どもの自己肯定感を高める
子どもにとって、「できた!」という体験は、大きな意味を持ちます。
跳び箱のように少し難しいことに挑戦し、それを乗り越えたときの喜びは、
自己肯定感の土台となるのです。
最初は跳べなかった子が、何度も挑戦を重ねて少しずつ前に進む。
先生や仲間の応援を受けながら、ついに跳び越えられたとき、
その笑顔には達成感と自信があふれています。
こうした成功体験は、運動だけでなく、学習や人間関係など他の場面でも大きな支えになります。
「やればできる」「頑張ってよかった」という気持ちが、これからの成長をぐっと後押ししてくれます。



「跳べた瞬間の“やった!”という顔、あれが自信に変わる第一歩なんです。」
運動教室to JOYでの跳び箱の取り入れ方
「跳び箱が苦手な子でも、楽しめる教室があったらいいのに」
そう思ったことはありませんか?
三重県松阪市にある
こども運動教室to JOY(トゥージョイ)
では、跳び箱を「できる・できない」で終わらせず、
一人ひとりの“やってみたい気持ち”を大切にしたプログラムを提供しています。
高く跳ぶことよりも、まずは楽しみながら体を動かすこと。
子どもたちが自然と「挑戦してみたい」と思えるよう、跳び箱に触れるステップも工夫しています。
ここでは、to JOYが実際に取り入れている跳び箱指導の特徴や、
子どもたちが前向きになれる仕掛けをご紹介します。
「遊びながら挑戦できる」段階式プログラム
to JOYの跳び箱プログラムは、「いきなり跳ぶ」ことを目標にしていません。
まずは、跳び箱に慣れることからスタートします。
最初のステップは、跳び箱の上に手を置いて「またぐ」だけ。
そこから、跳び箱に軽く乗ってみる、踏み台を使って跳ぶ感覚をつかむ、というふうに、
段階的に少しずつレベルアップできる構成になっています。
この工夫により、子どもたちは「できないからイヤ」ではなく、
「やってみたい!」という前向きな気持ちで取り組むことができるのです。
また、スタッフが常に近くで見守り、成功体験を逃さずに声をかけることで、
自信を積み重ねながら次のステップに進めるようになっています。
苦手な子が「跳べた!」に変わる瞬間
to JOYでは、跳び箱が苦手な子どもたちに寄り添ったサポートを行っています。
焦らず、一人ひとりのペースに合わせて進めることで、子ども自身が「やってみよう」と思えるようになるのです。
たとえば、最初は跳び箱の前に立つことすら緊張していた子が、
何度かの練習で足をしっかり踏み出し、スタッフの補助を受けながら跳び越えたとき――
その「できた!」という表情は、自信そのものです。
このような経験は、ただ跳べるようになる以上に、
子どもの心の中に「やればできる」という自己信頼を育ててくれます。



「あの子が跳べた瞬間、思わず拍手が出ました!本人の笑顔が忘れられません。」
楽しさを引き出す跳び箱アレンジ例
跳び箱=難しいというイメージを変えるには、「楽しい!」という感覚を育てることが大切です。
to JOYでは、跳び箱をゲーム感覚で取り入れたアレンジを行い、子どもたちが自然と体を動かしたくなる工夫をしています。
たとえば、跳び箱をくぐったり、乗ってポーズをとったり、動物の真似をしてジャンプしたり。
こうした遊びの中で、跳び箱に親しみを持ち、恐怖心を和らげていくのです。
また、色とりどりの踏み台やマットを使って、視覚的にもワクワクするようなコースを作ることもあります。
このように、跳び箱を“挑戦する道具”ではなく、“遊べるアイテム”として捉えることで、
子どもたちの意欲や笑顔が自然と引き出されていきます。


跳び箱が教えてくれるのは“心と体の成長”
跳び箱に取り組む中で、子どもたちは「跳べた!」という達成感だけでなく、
その過程で多くのことを学んでいます。
- 最初は怖くても、一歩踏み出す勇気
- 何度も挑戦する粘り強さ
- うまくいかないときに気持ちを切り替える力
- 仲間を応援したり、順番を守る協調性
これらはすべて、運動能力ではなく、非認知能力と呼ばれる“生きる力”につながる要素です。
跳び箱は、体だけでなく心の成長を育てる教材でもあります。
だからこそ、跳べる・跳べないに関係なく、取り組む価値があるのです。



「非認知能力って、運動からも育つんですよ。跳び箱はまさに“心を育てる種目”なんです。」
跳び箱を通じて育まれる、子どもたちの未来力
今回は跳び箱の意味や教育的な価値、そしてto JOYでの取り組みについてご紹介しました。
跳び箱は、「跳べるかどうか」だけでは測れない、たくさんの力を育てる運動です。
- 基礎的な運動能力(瞬発力・バランス感覚など)
- 心の成長(挑戦する気持ち・達成感・非認知能力)
- 他者との関わり(応援・順番・協調性)
to JOYでは、こうした力を自然に伸ばせるよう、楽しく安心できる跳び箱プログラムを用意しています。
私たちの教室「こども運動教室to JOY(トゥージョイ)」では「KaRaDaStyle」のソフト跳び箱を導入しています。




自宅でも使いやすく、 お手頃な価格で購入できますので、 お子様へのプレゼントにも最適です。
他の記事で、ソフト跳び箱のおすすめ3選を 紹介しています。プレゼントの購入はこちらから参照していただければ幸いです。


跳び箱が苦手でも大丈夫。小さな「できた!」の積み重ねが、子どもたちの未来を支えてくれると信じています。



「お子さんの『できた!』を、私たちと一緒に増やしていきませんか?」
「うちの子、運動が苦手かも…」
そんな保護者の声に応えるのが、
三重県松阪市のサンパーク1階『こども運動教室 to JOY(トゥージョイ)』です。


to JOYでは、従来の体操教室やスポーツ少年団ではなく、
こども運動教室to JOYではこどもに合った活用方法が見つかる!
- 苦手な運動が 人目を気にせずに克服できる「パーソナルレッスン」
- きょうだいや友達と一緒に受けられる「グループレッスン」
- 雨・酷暑・ 花粉が 厳しい時期でも自由に遊べる「室内公園」



👉 詳しくはto JOY公式ページ、公式インスタグラム、
申し込みやご質問は公式ラインでお待ちしております。



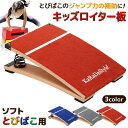






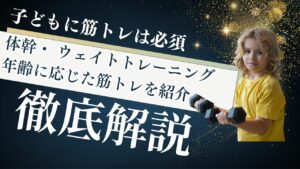


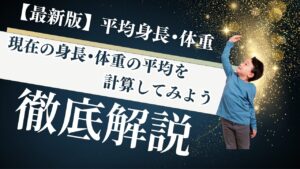

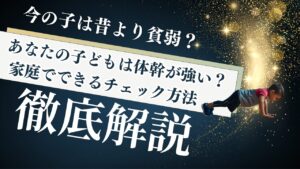
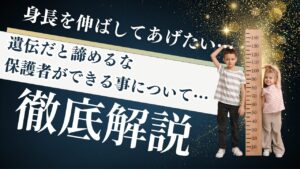
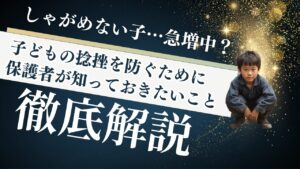
コメント