運動神経が悪い子どもの特徴とは?専門家が家庭でできる伸ばし方も解説

「うちの子、運動神経が悪いのかも…」 「周りの子と比べて動きがぎこちない気がする」
そんなふうに悩んでいる保護者の方は、決して少なくありません。 実際、子どもの動きに関する不安は、年代を問わず多くの親が抱える共通のテーマです。
でも安心してください。
「運動神経が悪いように見える子」も、ちょっとした工夫で大きく伸びる可能性を秘めています。
この記事では、子どもの運動神経が悪く見える特徴やその原因、家庭でできるサポート方法、 そして必要に応じて活用したい運動教室まで、わかりやすく解説していきます。
「できない」から「できた!」へ。 今日から始められる小さな工夫で、お子さんの可能性を一緒に伸ばしていきましょう。

片山 拳心(KATAYAMA KENSHIN)
三重県松阪市のサンパーク1階で、こども運動教室to JOY(トゥージョイ)の代表を務めています。
キッズスイミングスクールやフィットネスジムでの指導経験に加え、消防士として多くの現場にも携わってきました。
現在は、消防を退職後に、科学的根拠に基づく安全で楽しい運動教室を開業。
保有資格
- 運動遊び実践サブリーダー(NPO運動保育士会)
- 子育て脳機能アドバイザー/ディレクター
- 幼児運動遊び実践アシスタント
- キッズコーディネーショントレーナー(KCT)
- (一社)スポーツリズムトレーニング協会認定
・ アドバンスドディフューザー(AD)
・ リズムステップディフューザー(DF)
著者の片山が代表を務める運動教室情報
「うちの子、運動が苦手かも…」
そんな保護者の声に応えるのが、
三重県松阪市のサンパーク1階『こども運動教室 to JOY(トゥージョイ)』です。

to JOYでは、従来の体操教室やスポーツ少年団ではなく、
こども運動教室to JOYではこどもに合った活用方法が見つかる!
- 苦手な運動が 人目を気にせずに克服できる「パーソナルレッスン」
- きょうだいや友達と一緒に受けられる「グループレッスン」
- 雨・酷暑・ 花粉が 厳しい時期でも自由に遊べる「室内公園」
 片山 拳心
片山 拳心👉 詳しくはto JOY公式ページ、公式インスタグラム、
申し込みやご質問は公式ラインでお待ちしております。
子どもの「運動神経が悪いかも?」と思う瞬間
親として日常生活の中で、「うちの子、運動が苦手かも…」と感じることはありませんか? 実は、運動神経に関する不安は多くの保護者が感じている共通の悩みです。
しかし、どんな子どもにも“伸びるチャンス”は必ずあります。
まずは、運動神経が悪く見える場面や特徴を知ることから始めましょう。
走り方やボール投げがぎこちない
運動神経が気になる子どもの特徴として、最もわかりやすいのが走る・投げるといった基本動作のぎこちなさです。
例えば、腕を大きく振らずに足だけで走っていたり、ボールを投げるときに全身を使わず手先だけで動作を終えてしまったりと、周囲と比べて違和感を感じることが多いです。


また、本人も「どう動かしていいかわからない」という戸惑いを抱えていることが多く、無理にやらせようとするとさらに自信をなくすケースも見られます。
これは運動神経が「悪い」というよりも、体の連動性や空間認識がまだ未発達な状態であることがほとんどです。
親が焦らずに見守りながら、少しずつ動きを覚えさせることで、自然に動作がスムーズになっていきます。



「正しく動けていない=運動が苦手」と決めつけず、今どんなサポートができるかを考えることが、子どもの成長を後押しする第一歩です。
バランスを取るのが苦手でよく転ぶ
子どもが歩いたり走ったりしているとき、頻繁につまずいたり転んだりする様子が見られると、「運動神経が悪いのでは?」と感じてしまう保護者も多いでしょう。
特に段差がないところでもバランスを崩してしまう場合、体の軸がまだ安定していないことが考えられます。
また、片足立ちが苦手だったり、平均台の上を歩けなかったりするのも、バランス感覚の未発達が原因となっていることがあります。
これは運動能力というより、体幹や前庭感覚(バランス感覚)を育てる経験が不足しているサインです。
遊びを通じて楽しみながらバランスを取る練習を積むことで、自然と安定した動きができるようになります。
「転ぶから心配」と制限するのではなく、安全な範囲でどんどん動かすことが、将来の運動能力向上につながります。
運動を嫌がる・やりたがらない
「走ろう」「ボールで遊ぼう」と声をかけても、子どもがなかなか体を動かしたがらないことはありませんか?
運動そのものを避ける傾向がある子どもは、過去に「うまくできなかった」「恥ずかしかった」などの体験が影響している場合があります。
特に集団の中で運動する場面で失敗を経験すると、自己肯定感が下がり、それ以降やりたがらなくなるケースも少なくありません。
このような子どもには、まずは「できた!」を実感させることが大切です。


小さな成功体験を積み重ねることで、自信がつき、自ら「やってみよう」と思えるようになります。
「運動嫌い」は子どもの性格ではなく、環境や声かけ次第で大きく変わる可能性があるのです。
運動神経が悪く見える3つの主な原因
「運動神経が悪い」と言われる子どもたちには、実は共通する背景があります。
それは“運動能力そのもの”ではなく、環境や経験の差に起因していることが多いのです。
原因を正しく理解することで、今後どのように関わるべきかが見えてきます。
ここでは、よく見られる3つの原因を紹介します。
運動経験が少なく自信がない
子どもが「運動神経が悪い」と見える理由の一つに、これまでの運動経験の少なさがあります。
幼いころから体を動かす機会が少ないと、自然な動作が身につきにくくなります。
公園で走ったり、友だちとボール遊びをしたりする経験がないまま成長すると、
どうしても動きがぎこちなくなり、「自分は運動が苦手」と思い込んでしまいがちです。
「やったことがない」ことは「できない」につながり、
それが続くと「やりたくない」になってしまいます。
「どうせうまくいかない」「また失敗するかも」と感じてしまうと、
チャレンジする前から運動を避けるようになってしまうのです。


運動を好きになるには、まず「楽しく動く」ことから始めることが大切です。
いきなり運動が得意になる必要はありません。
まずは簡単な動きから少しずつ慣れていけばOKです。
親子で一緒に遊んだり、家の中でバランス遊びをしたりするだけでも、
「できた!」という小さな成功体験を重ねることができます。
その積み重ねが子どもに自信を与え、やがて「運動って楽しい」と感じるようになります。
成功体験が「やってみよう」という前向きな気持ちにつながるのです。
体幹やバランス感覚が未発達
運動中にふらついたり、すぐ転んでしまう子どもは、体幹やバランス感覚がまだ育ちきっていない可能性があります。
見た目ではわかりにくいですが、「まっすぐ立つ」「方向転換する」といった基本動作に苦労している子も多いです。
特に椅子にじっと座っていられない、片足立ちが苦手などの様子が見られる場合、
体の中心を支える筋肉(インナーマッスル)や、平衡感覚をつかさどる神経の発達が未熟な状態だと考えられます。


このような子は運動をするとすぐ疲れたり、転倒への恐怖から動きがぎこちなくなってしまいがちです。
実際は能力の問題ではなく、「まだ使い方を学んでいないだけ」なのです。
遊びの中で自然に体幹やバランス感覚を刺激することが、スムーズな動きを育てる第一歩になります。
たとえば、不安定なクッションの上で遊ぶ、バランスボードに乗るなど、楽しみながら体の中心を使う運動が効果的です。
親が「うまく立てたね」「前より安定してるよ」とポジティブな声かけをすることで、
子ども自身も「やってみよう」と意欲的になれます。
基礎的な体の力は、トレーニングというより「遊びの工夫」で自然に身につくもの。
体幹が整ってくると、他の運動も驚くほどスムーズにできるようになります。
発達段階の個人差や性格も影響する
子どもの運動能力には、発達段階による個人差があります。
同じ年齢でも、神経系や筋肉の発達スピードにはかなりの幅があるため、比較することにあまり意味はありません。
たとえば、「6歳なのにまだジャンプがうまくできない」と悩むことがあるかもしれませんが、
それは単に、その子の発達が少しゆっくりなだけということも多いのです。
また、子ども自身の性格も運動への取り組みに影響を与えます。
慎重な子や完璧主義な子は、「できないこと」に対して強く反応しやすく、挑戦を避けてしまう傾向があります。
逆に、活発な子であっても失敗が続くと自信をなくし、「ぼくは運動が苦手なんだ」と思い込んでしまうこともあります。
一人ひとりの特性を理解し、成長のペースを尊重することが、運動能力の向上につながります。
他の子と比べるのではなく、「昨日の自分」と比べて少しでもできたら、それを褒めてあげましょう。
小さな進歩に気づいてあげることで、子どものやる気は自然と引き出されます。
発達は「早い・遅い」ではなく「その子に合ったペース」です。
その理解が、親としてできる最大のサポートになります。
家庭でできる運動神経アップのアプローチ
運動が苦手に見える子どもでも、日々の生活の中で無理なくできる工夫で、運動能力を少しずつ高めていくことができます。
特別なトレーニングや高価な道具は必要ありません。
大切なのは、「運動=つらいもの」ではなく、
「運動=楽しい!」と思える体験を積み重ねることです。
ここでは、家庭で手軽に始められる実践的なアプローチを3つご紹介します。
遊び感覚でできる運動メニュー
運動神経を育てるには、「楽しさ」をベースにした遊びの中で自然に体を動かすことが最も効果的です。
運動が苦手な子でも、遊びの延長であれば抵抗なくチャレンジできます。
たとえば、床にテープで線を貼って「線の上を歩く平均台ごっこ」、
クッションを飛び越える「ジャンプチャレンジ」など、
家にあるものでできる簡単なメニューがたくさんあります。
また、紙コップを並べて蹴飛ばしたり、ぬいぐるみを投げて的に当てる遊びも、
体のコントロール力や集中力を鍛えるのにぴったりです。
「遊びながら自然に運動できている」状態が、子どもの運動神経を伸ばす理想の環境です。
運動の得意・不得意を意識させないことが、苦手意識を作らないカギです。
ゲーム感覚で楽しみながら続けることで、「動くのって面白い!」という気持ちが育っていきます。



毎日ほんの5分でも良いので、親子で一緒に笑顔で体を動かしてみてください。
その時間の積み重ねが、将来の大きな自信へとつながります。
親子で一緒に取り組む工夫
運動に苦手意識を持っている子どもにとって、ひとりでやる運動はハードルが高く感じられることがあります。
そんなときに力になるのが、親子で一緒に取り組むスタイルです。
「お母さんも一緒にやるよ」「競争してみようか」と声をかけるだけで、
子どもは安心感を得て、楽しみながらチャレンジできるようになります。
家の中でできる「親子で手をつないでバランス遊び」や「タオルを使った引っ張りっこ」など、
触れ合いながらできる運動は、信頼関係を深めるきっかけにもなります。
親子で笑いながら体を動かす時間は、運動神経だけでなく心の発達にも大きなプラスになります。



運動に限らず、「大人が本気で楽しんでいる姿」を見せることで、子どもも前向きになれます。
頑張りすぎず、日常の延長で自然に取り入れていけると理想的です。
「運動=家族の楽しい時間」というイメージを育てていきましょう。
成功体験を積ませる声かけのコツ
子どもが運動を好きになるためには、「できた!」という成功体験を積み重ねることがとても重要です。
そのためには、大人の声かけが大きなカギを握っています。
「すごい!」「上手だね」といった結果を褒める言葉も効果的ですが、
それ以上に、「挑戦したね」「前より早くなったね」といった過程を認める言葉が、
子どもの自信を育てる力になります。


特に運動が苦手な子どもは、成功体験が少なく「どうせできない」と感じてしまいがちです。
だからこそ、小さな変化や努力にも気づいて声をかけることが大切です。
「やってみた自分ってすごい」と思える声かけは、次の挑戦につながる原動力になります。
たとえ失敗しても、「がんばったね」と肯定することで、子どもはまた挑戦しようと思えます。
この積み重ねが、やがて「運動って楽しいかも」という気持ちにつながっていくのです。
声かけは技術ではなく「観察力」と「愛情」です。
子どもの変化を見逃さず、心からの言葉で応援してあげましょう。
運動神経が悪いと感じても、子どもはこれから伸びる!
これまで、子どもの運動神経が「悪い」と感じる原因や、
家庭でできるサポート方法、教室を活用する選択肢についてご紹介してきました。
大切なのは、「できない今」ではなく「これからの可能性」に目を向けることです。
運動は生まれつきの才能ではなく、日々の積み重ねで大きく変わる分野です。
環境や声かけ、遊びの工夫ひとつで、子どもの動きは驚くほどスムーズになります。
焦らず、比べず、子どもの「できた!」を一緒に喜ぶことが成長への第一歩です。
今日からできることはたくさんあります。
家の中での簡単な運動遊び、ポジティブな声かけ、そして「一緒にやってみよう」の一言。
こうした積み重ねが、やがて子どもに「運動って楽しいかも」という気持ちを芽生えさせてくれます。
今回は「運動神経が悪い子どもの特徴と、家庭でできるサポート方法」についてご説明しました。
「うちの子、苦手かも…」と思ったその時こそ、サポートを始めるタイミングです。
まずは今日、たった5分でも、親子で体を動かしてみることから始めてみませんか?



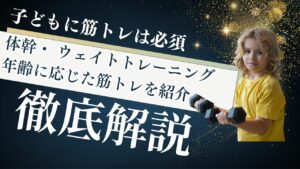


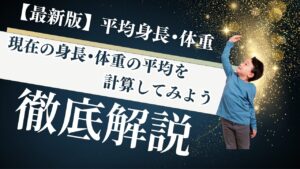

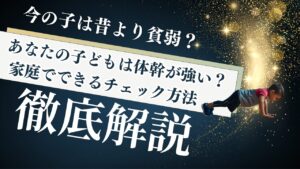
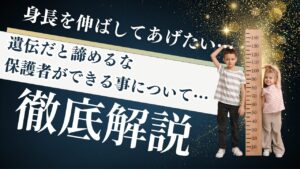
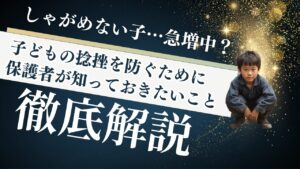
コメント