子どもにぴったりの粘土は?種類ごとの特徴と選び方を徹底解説
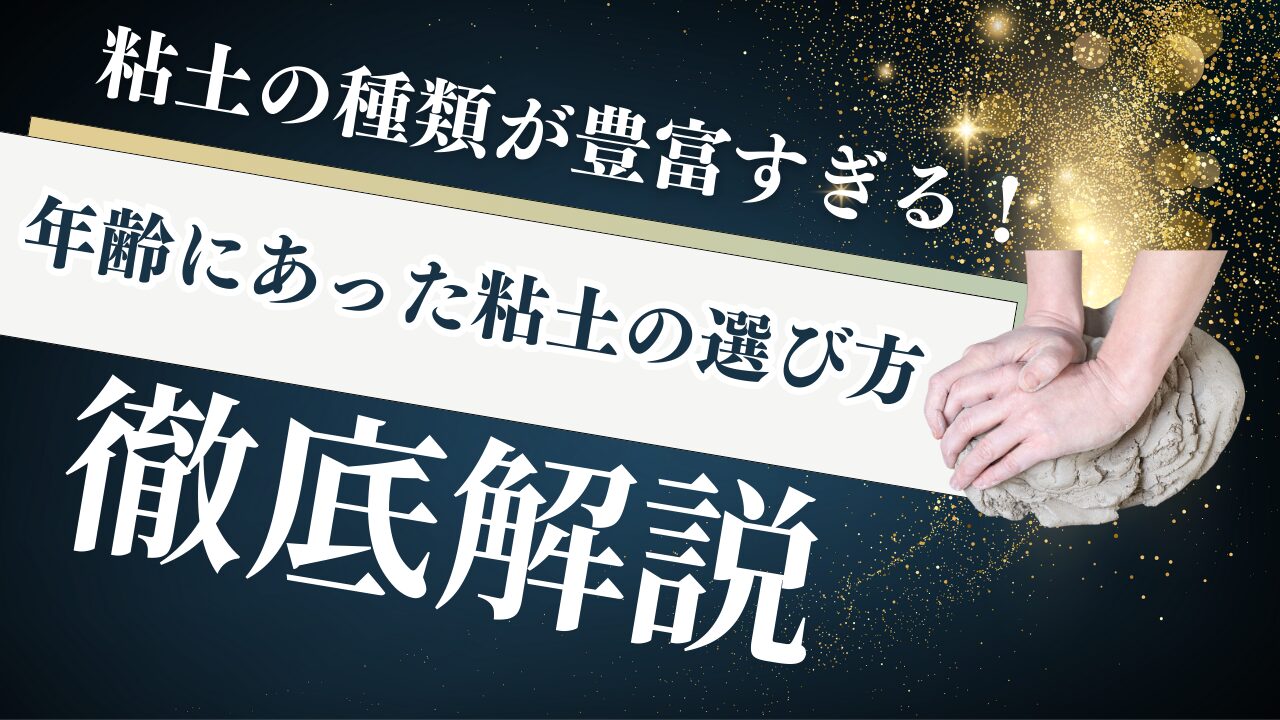
子どもに粘土を選ぶとき、まず気になるのが「どんな種類があるのか」という点ではないでしょうか。
ひとくちに粘土といっても、素材や性質によって使い心地や遊び方が大きく異なります。
ここでは、子ども向けによく使われている粘土を4種類に分けてご紹介します。
それぞれの特徴を知っておくと、お子さんの年齢や性格、遊ぶ目的にぴったりの粘土を選ぶことができます。

片山 拳心(KATAYAMA KENSHIN)
三重県松阪市のサンパーク1階で、こども運動教室to JOY(トゥージョイ)の代表を務めています。
キッズスイミングスクールやフィットネスジムでの指導経験に加え、消防士として多くの現場にも携わってきました。
現在は、消防を退職後に、科学的根拠に基づく安全で楽しい運動教室を開業。
保有資格
- 運動遊び実践サブリーダー(NPO運動保育士会)
- 子育て脳機能アドバイザー/ディレクター
- 幼児運動遊び実践アシスタント
- キッズコーディネーショントレーナー(KCT)
- (一社)スポーツリズムトレーニング協会認定
・ アドバンスドディフューザー(AD)
・ リズムステップディフューザー(DF)
粘土の種類を知ろう|子どもに人気の4タイプ
主な粘土の種類は以下の4つです。
- 油粘土
- 紙粘土
- 小麦・米粉粘土
- 樹脂粘土・石粉粘土
それでは本章では、代表的な粘土の種類と特徴について、順に見ていきましょう。
油粘土(繰り返し遊びたい子に)
油粘土は、子どもが何度も形を作って遊ぶのに向いている、定番の粘土です。
空気に触れても乾燥しにくく、柔らかさが長く続くため、長時間遊んでも固まらず、繰り返し使えるのが大きな特徴です。
油を含んでいるためベタつきやにおいがややありますが、適度な弾力があり、力の弱い子どもでも扱いやすい素材です。
また、乾かないという特性から、完成品を保存するのではなく、自由な創作を楽しむ目的に向いています。
粘土遊びを通じて「作る→壊す→また作る」というプロセスを楽しませたいときには、油粘土がぴったりです。
紙粘土(乾かして作品づくりに)
紙粘土は、空気に触れると自然に乾いて固まるタイプの粘土です。
乾いた後は絵の具などで着色できるため、作品を作って飾ることに適しています。
もともとが軽くて扱いやすく、粘土細工の入門としても人気があります。
乾燥によって形が固定されるので、「何かを作って完成させたい」という子どもにおすすめです。
ただし、乾くとひび割れが起きやすい場合もあるため、遊んでいる途中で乾かないように注意が必要です。
使用後は密閉して保管し、乾燥を防ぐようにしましょう。
小麦・米粉粘土(誤飲が心配な子にも)
小麦や米粉から作られた粘土は、食品由来の素材を使っているため、誤って口に入れてしまっても安心という特徴があります。
そのため、特に1〜2歳の小さな子どもに人気があり、「はじめての粘土あそび」に選ばれることが多い種類です。
やわらかくてちぎりやすく、香りや色もやさしいものが多いため、感触を楽しみながら遊ぶのに適しています。
保育園や子育て支援施設などでも広く使われており、安心感と扱いやすさを兼ね備えた粘土といえるでしょう。
ただし、小麦を使っているため、小麦アレルギーのある子には注意が必要です。
その場合は、米粉粘土など別の素材を選ぶことで、同じように安全に遊ぶことができます。
 片山 拳心
片山 拳心to JOYパークでは、小さなお子さんにも安心して楽しんでもらえるように、小麦粘土を使用しています。
樹脂粘土・石粉粘土(細かい造形を楽しみたいときに)
樹脂粘土や石粉粘土は、繊細な作品づくりや細かい造形を楽しみたいときに適した粘土です。
乾燥後にしっかりと硬くなり、強度があるため、アクセサリーや模型、フィギュアなどの工作にも使用されます。
樹脂粘土は、乾くと透明感やツヤが出るタイプも多く、完成後に絵の具で塗ったりニスを塗ったりすることで、作品の表現の幅が広がります。
一方、石粉粘土はマットな質感で、木や石のような自然な仕上がりが特徴です。
いずれも扱いには少しコツが必要で、小さな子どもにはやや難易度が高い場合もあります。
しかし、手先が器用になってきた年齢の子や、「本格的なものを作ってみたい」という意欲のある子には、ものづくりの楽しさを広げてくれる粘土です。
年齢や遊び方で選ぶ|おすすめ粘土の種類と使い分け
粘土を選ぶときには、素材や特徴だけでなく、子どもの年齢や遊び方に合わせて選ぶことも大切です。
成長の段階によって、楽しめる粘土のタイプや、安全に扱える粘土が変わってくるためです。
たとえば、まだ手先がうまく使えない時期の子には感触を楽しむ粘土が向いていますし、形を作る力がついてきた子には作品づくりができる粘土がぴったりです。
年齢別のおすすめ粘土は、次のとおりです。
- 1〜2歳:小麦粘土・米粉粘土など、やわらかくて安心な素材
- 3〜5歳:油粘土や紙粘土で、形づくりや自由な創作を楽しむ
- 小学生以上:樹脂粘土や石粉粘土で、細かい作品づくりに挑戦
それでは本章では、年齢ごとにおすすめの粘土の種類と、その選び方のポイントについてご紹介します。
1〜2歳におすすめ|安心素材で「感触あそび」
1〜2歳の子どもにとって、粘土あそびは「形を作る」よりも、「触って感じる」ことが中心になります。
この時期は手先の発達がまだ未熟なため、強くこねたり細かい作業をするのは難しいものです。
そのため、感触を楽しめるようなやわらかい粘土が最適です。
特におすすめなのが、小麦粘土や米粉粘土など、食品由来の安全な素材で作られた粘土です。
「にぎる」「ちぎる」「つぶす」といったシンプルな動きでも十分に楽しめ、感覚刺激や手の発達を促す遊びになります。
万が一、粘土を口に入れてしまっても比較的安心できる点も、保護者にとって大きな安心材料です。
また、色や香りがやさしく設計されているものも多く、はじめて粘土に触れる子にぴったりの選択肢といえるでしょう。
3〜5歳におすすめ|こねて形を作る粘土遊び
3〜5歳になると、手先の器用さが発達し、イメージしたものを形にする力が育ってきます。
この時期の子どもは、「○○を作りたい!」という気持ちが芽生えはじめ、創造力を使ったあそびが楽しくなってくる頃です。
この年齢におすすめなのが、油粘土や紙粘土など、ほどよい弾力と扱いやすさを兼ね備えた粘土です。
油粘土は繰り返し使えるため、何度も作って壊してというプロセスを楽しむのにぴったり。
紙粘土は、乾燥させて形を残せるので、「作品を完成させる」達成感を味わうことができます。
また、粘土用の型や道具を使うことで、指先の使い方や空間認識の力も自然に育ちます。子どもが自分のイメージを表現する楽しさを知る、大切な時期といえるでしょう。
小学生以上におすすめ|作品づくりや模型にも挑戦
小学生になると、粘土での造形力がぐっと高まり、「作りたいものを形にする」ことがより具体的にできるようになります。
この時期には、仕上がりや表現の細かさにもこだわる子が増えてくるため、本格的な作品づくりに対応できる粘土を選ぶのがおすすめです。
たとえば、石粉粘土や樹脂粘土は、乾燥するとしっかりと硬くなり、耐久性のある作品に仕上がります。
細かいパーツの造形や、着色・ニスなどの仕上げ作業にも適しているため、工作や自由研究の素材としても活躍します。
また、オーブン粘土などを使えば、焼き固めてアクセサリーや雑貨を作ることも可能です。
「作品を完成させて飾る・使う」という達成感は、ものづくりの自信や集中力を育てる経験にもつながります。
粘土の種類で迷ったら?選び方のポイント3つ
粘土売り場にはたくさんの種類が並んでいて、初めて選ぶときは「どれがいいのかわからない」と迷ってしまうこともあるでしょう。
とくに小さな子どもに使わせる場合は、安全性や遊びやすさなど、気をつけたい点がいくつかあります。
ここでは、粘土を選ぶときに知っておきたい3つの基本ポイントをご紹介します。
素材の違いだけでなく、使う場面や子どもの性格もふまえて選ぶヒントになります。
選ぶときにチェックしたいポイントは次の3つです。
- 乾く粘土か、乾かない粘土かを確認する
- 安全性やアレルギーへの配慮がされているかを見る
- 汚れにくさや片づけやすさも意外と重要
それでは本章では、粘土選びでチェックしたい具体的なポイントを見ていきましょう。
乾く粘土か、乾かない粘土かで分けて考える
粘土を選ぶときにまず注目したいのが、「乾くタイプ」か「乾かないタイプ」かという違いです。
この性質によって、遊び方や使う目的が大きく変わってきます。
乾かない粘土(例:油粘土)は、何度でも繰り返し遊べるのが最大のメリットです。
毎回形を変えて遊びたい子どもや、作ったものを保存しない場合に向いています。
一方、乾く粘土(例:紙粘土や石粉粘土)は、空気に触れると固まって形が残ります。
完成させた作品を飾ったり、色を塗って楽しんだりしたいときにおすすめです。
「長く使いたい」か「形を残したい」か、目的に合わせてタイプを選ぶことで、子どもにとっての満足度が変わります。



乾く粘土で作った作品を残しておくと、“〇歳のときにこんなのが作れた”っていう成長の記録にもなりますよ。
安全性・アレルギーの心配はある?
小さな子どもに粘土を使わせる際には、素材の安全性やアレルギーへの配慮も大切なチェックポイントです。
特に1〜3歳ごろの子どもは、遊びながら粘土を口に入れてしまうこともあります。
そのため、食品由来の素材(小麦・米粉など)を使った粘土や、無害で誤飲しても安全性が高いとされる製品を選ぶと安心です。
一方で、小麦粘土には小麦アレルギーの心配もあるため、体質に合った粘土を選ぶことが重要です。
近年は、米粉粘土やアレルゲンフリーの製品も増えており、アレルギーが気になる場合はパッケージの表示をしっかり確認しましょう。
また、香料・着色料の有無も確認ポイントのひとつです。なるべく無香料・無着色のシンプルなタイプを選べば、肌への刺激も少なく安心して使えます。
汚れやすさ・片づけやすさも大事なポイント
粘土あそびは楽しい反面、床や服が汚れやすいという心配もあります。
特に家庭で使う場合、後片づけのしやすさは保護者にとって大事な選択基準のひとつです。
油粘土は、乾かない分だけ粘着力があり、テーブルや手にベタつきが残りやすい特徴があります。
新聞紙や専用マットを敷くことで汚れを防ぐことができますが、遊んだあとはしっかり拭き取りが必要です。
一方、紙粘土や小麦粘土は水分を含んでおり、乾燥すればポロポロとカスが出ることがあります。
床に落ちた破片は掃除機で簡単に取れますが、遊ぶ場所を決めておくと片づけがスムーズです。
また、保存のしやすさも選ぶ際のポイントです。乾きやすい粘土は密閉容器に入れて保管しないとすぐに使えなくなってしまうため、袋のチャック付きかどうかなども確認しておくと安心です。
粘土選びは「年齢・目的・安全性」で考えよう
今回は、子ども向けの粘土の種類や選び方についてご紹介しました。
ひとくちに粘土といっても、素材や特性はさまざまで、子どもの年齢や遊び方、家庭での使いやすさによって最適な粘土は変わってきます。
繰り返し遊びたいなら油粘土、作品を残したいなら紙粘土、安心して遊ばせたいなら小麦・米粉粘土、本格的に作品づくりをしたいなら樹脂粘土や石粉粘土が適しています。
子どもが楽しく、そして安心して粘土遊びを楽しめるように、用途に合わせた粘土をぜひ取り入れてみてください。
年齢とともに粘土の種類を変えていくことで、創造力や表現力の広がりもぐんと育っていきます。
\ かたやま代表の子育てお役立てコラム /
-


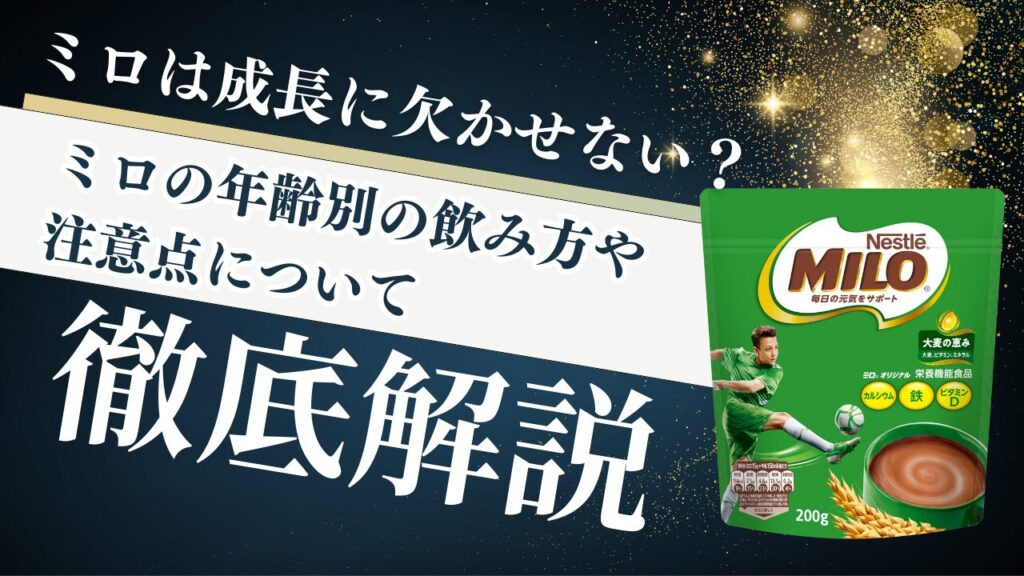
ミロは何歳から飲める?子どもの成長と女性におすすめな理由も解説
「ミロって何歳から飲ませても大丈夫?」 「栄養はあるけど糖分が心配…」 そんな疑問を持つ保護者の方も多いのではないでしょうか。 ミロは何歳から飲むことができる… -



プロ監修!子どものプレゼントに最適な自宅用ソフト跳び箱おすすめ【3選】
「最近ゲームばかりで、ぜんぜん体を動かしてないな…」 「プレゼントするなら、運動神経の向上に役に立つものにしたい」 そんなふうに思ったことはありませんか? この… -



運動神経が悪い子どもの特徴とは?専門家が家庭でできる伸ばし方も解説
「うちの子、運動神経が悪いのかも…」 「周りの子と比べて動きがぎこちない気がする」 そんなふうに悩んでいる保護者の方は、決して少なくありません。 実際、子どもの…
「うちの子、運動が苦手かも…」
そんな保護者の声に応えるのが、
三重県松阪市のサンパーク1階『こども運動教室 to JOY(トゥージョイ)』です。


to JOYでは、従来の体操教室やスポーツ少年団ではなく、
こども運動教室to JOYではこどもに合った活用方法が見つかる!
- 苦手な運動が 人目を気にせずに克服できる「パーソナルレッスン」
- きょうだいや友達と一緒に受けられる「グループレッスン」
- 雨・酷暑・ 花粉が 厳しい時期でも自由に遊べる「室内公園」



👉 詳しくはto JOY公式ページ、公式インスタグラム、
申し込みやご質問は公式ラインでお待ちしております。

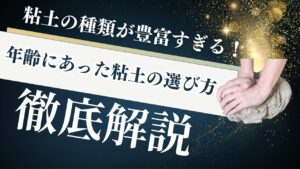

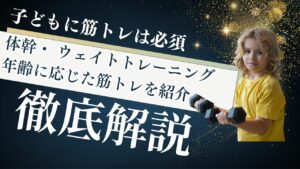


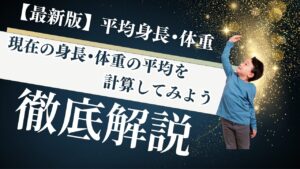

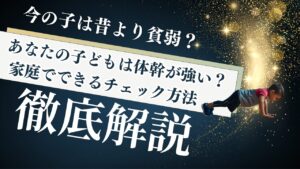
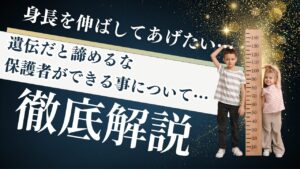
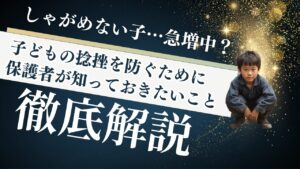
コメント