こどもの理想的な睡眠時間とは?9時間睡眠がもたらす驚きの効果とは
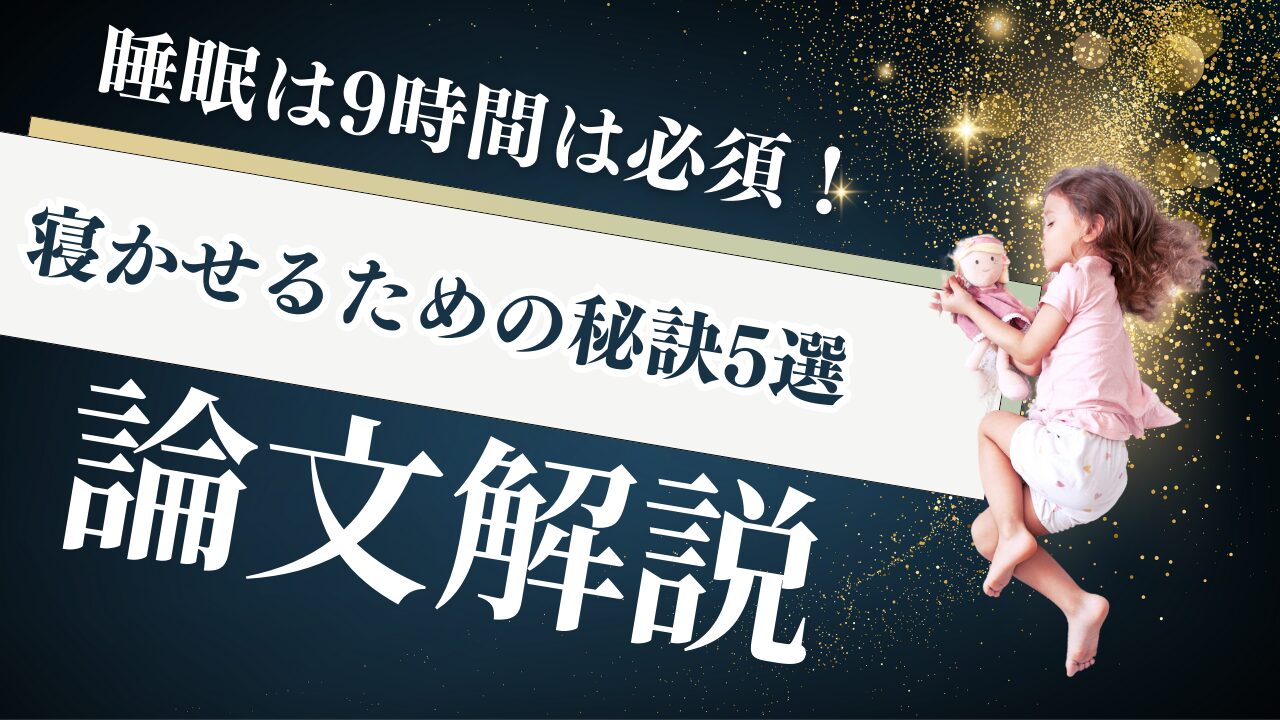

片山 拳心(KATAYAMA KENSHIN)
三重県松阪市のサンパーク1階で、こども運動教室to JOY(トゥージョイ)の代表を務めています。
キッズスイミングスクールやフィットネスジムでの指導経験に加え、消防士として多くの現場にも携わってきました。
現在は、消防を退職後に、科学的根拠に基づく安全で楽しい運動教室を開業。
保有資格
- 運動遊び実践サブリーダー(NPO運動保育士会)
- 子育て脳機能アドバイザー/ディレクター
- 幼児運動遊び実践アシスタント
- キッズコーディネーショントレーナー(KCT)
- (一社)スポーツリズムトレーニング協会認定
・ アドバンスドディフューザー(AD)
・ リズムステップディフューザー(DF)
「うちの子、夜寝るのがどんどん遅くなっている気がする……」
「毎朝起きるのがつらそうで、学校生活に支障が出ないか心配……」
そんな悩みを抱える保護者の方も多いのではないでしょうか。
実は、睡眠不足は一時的な疲れや不機嫌にとどまらず、子どもの脳や心、体の発達に大きな影響を与えることがわかっています。
しかし、ご安心ください。
世界中の最新研究により、こどもが「理想的な睡眠時間」を確保するための具体的な方法が明らかになっています。
この記事では、科学的な根拠に基づいた5つの改善策をご紹介します。
読み終わる頃には、今夜からすぐに実践できるヒントを手に入れ、お子さんの未来を守るための第一歩を踏み出せるはずです。
著者の片山が代表を務める運動教室情報
「うちの子、運動が苦手かも…」
そんな保護者の声に応えるのが、
三重県松阪市のサンパーク1階『こども運動教室 to JOY(トゥージョイ)』です。

to JOYでは、従来の体操教室やスポーツ少年団ではなく、
こども運動教室to JOYではこどもに合った活用方法が見つかる!
- 苦手な運動が 人目を気にせずに克服できる「パーソナルレッスン」
- きょうだいや友達と一緒に受けられる「グループレッスン」
- 雨・酷暑・ 花粉が 厳しい時期でも自由に遊べる「室内公園」
 片山 拳心
片山 拳心👉 詳しくはto JOY公式ページ、公式インスタグラム、
申し込みやご質問は公式ラインでお待ちしております。
こどもの理想的な睡眠時間はどれくらい?
小学生の子どもには毎晩9〜12時間、中高生でも8〜10時間の睡眠が必要です。
これらの時間をしっかり確保することで、集中力・記憶力・感情コントロールなどが向上し、脳と心の発達が健全に促されます。
特に、最新の研究では「9時間以上の睡眠」をとる子どもは、学業成績や精神的健康が優れていることが証明されています。
年齢に応じた理想の睡眠時間を理解し、子どもたちの健やかな成長を支えていきましょう。
年齢別に見る「理想の睡眠時間」ガイド
子どもの睡眠に必要な時間は、成長段階によって大きく異なります。
米国睡眠医学会(AASM)の推奨する年齢別の理想的な睡眠時間は、以下のとおりです。
- 乳幼児(1〜2歳):11〜14時間
- 未就学児(3〜5歳):10〜13時間
- 小学生(6〜12歳):9〜12時間
- 中高生(13〜18歳):8〜10時間
小学生の時期は、脳の神経ネットワークが急速に発達する重要な期間です。
このため、毎晩9〜12時間のたっぷりとした睡眠を確保することが不可欠です。
睡眠不足は、日中の注意力低下や記憶力の低下を引き起こし、学業パフォーマンスにも悪影響を与えます。
成長期の子どもたちには、「夜しっかり眠ること」が未来への大きな投資となるのです。
9時間睡眠がなぜ必要なのか?最新研究が示す理由
米国で行われた大規模研究、Longitudinal association between sleep duration and neurocognitive development in early adolescenceでは、9〜10歳の子どもたち約11,000人を対象に、睡眠時間と脳・心の発達の関係が調査されました。
その結果、
9時間以上眠った子どもは、注意力や問題解決力、記憶力が高い
不安やうつ症状が少なく、精神的に安定している
脳の前頭前野や頭頂葉の灰白質量が多く、脳の発達が良好
ということが明らかになりました。
逆に9時間未満の睡眠では、脳の成長が妨げられ、感情の不安定さや学力の低下といった悪影響が見られました。
つまり、毎晩9時間以上眠ることは、子どもの知能・感情・健康すべてを支える土台だといえます。
睡眠不足がこどもに与える悪影響
こどもが必要な睡眠時間を確保できないと、集中力や記憶力の低下、感情の不安定化、さらには免疫力の低下や成長の妨げにつながるリスクがあります。
睡眠不足は一時的な疲労感だけでなく、脳や心、体の発達そのものに長期的な悪影響を及ぼすことがわかっています。
ここでは、睡眠不足が子どもにどのような問題を引き起こすのか、具体的に見ていきましょう。
集中力・学業成績への悪影響
睡眠が不足すると、子どもの脳は情報をうまく整理できず、日中の注意力が著しく低下します。
米国睡眠医学会(AASM)の報告によると、睡眠不足の子どもは、学校でのテスト結果や課題のパフォーマンスに悪影響を受けやすいことが示されています。
また、十分な睡眠をとった場合に比べ、反応速度や記憶力も大幅に低下し、学びの効率が悪くなります。
日々の積み重ねが重要な子どもたちにとって、睡眠不足は「学びの質そのもの」を下げてしまう危険因子といえるでしょう。
メンタルヘルスへのリスク
睡眠不足は、単なる眠気にとどまらず、子どもの精神的な健康にも大きな影響を及ぼします。
複数の研究では、睡眠時間が短い子どもほど、うつ傾向や不安感を抱きやすくなることが報告されています。
睡眠は脳の感情をコントロールする部位(扁桃体や前頭前野)を整える重要な役割を果たしており、
このバランスが崩れると、感情のコントロールが難しくなり、イライラや悲しみを強く感じやすくなります。
特に思春期に入る前後の子どもたちにとって、良質な睡眠はメンタルヘルスを守る「盾」のような存在なのです。
体の成長・免疫力へのマイナス影響
成長期の子どもにとって、睡眠中に分泌される成長ホルモンは非常に重要な役割を担っています。
しかし、睡眠不足が続くと、この成長ホルモンの分泌量が低下し、骨や筋肉の発達にも悪影響を与える可能性があります。
また、睡眠中には免疫細胞が活性化し、ウイルスや細菌への抵抗力を高めています。
十分な睡眠がとれない子どもは、風邪や感染症にかかりやすくなり、体調を崩しやすくなるというリスクも指摘されています。
健やかな体作りのためにも、毎晩の十分な睡眠は欠かせないのです。
今日からできる!こどもの睡眠時間を確保する具体的な5つの方法
今回は、世界のさまざまな研究から効果が実証された「こどもの睡眠時間を確保する5つの方法」をご紹介します。
単なる生活習慣のアドバイスではなく、実際に科学的な裏付けがある具体策です。
子どもの理想的な睡眠を守るためには、家庭全体での取り組みが不可欠です。
この記事では、今日からすぐに実践できる5つのポイントを、最新の論文データとともに詳しく解説していきます。
一貫した就寝ルーティンを作る
毎晩同じ流れで行動する「就寝ルーティン」は、子どもの体内時計を整え、自然な眠気を促すために非常に効果的です。
就寝前の決まった行動が、脳に「これから寝る時間だ」と信号を送り、スムーズな入眠を助けます。
たとえば、次のような流れを毎晩繰り返すことが推奨されています。
- 20:00 テレビやゲームを終了する
- 20:15 入浴と歯磨きを済ませる
- 20:30 部屋を暗くして絵本の読み聞かせ
- 21:00 ベッドに入り、リラックスした雰囲気で就寝
この一貫したパターンを1〜2週間続けるだけで、寝つきが良くなり、夜中の覚醒も減少すると報告されています。



「眠るための合図」を毎晩脳に与えることが、良質な睡眠の第一歩です。
参考論文:Bedtime Routines for Young Children: A Review of Evidence and Best Practices (PMID: 9327577)
就寝前のスマホ・タブレット使用を制限する
スマホやタブレットの光に含まれるブルーライトは、脳の覚醒レベルを高め、睡眠ホルモン「メラトニン」の分泌を抑制してしまいます。
これにより、寝つきが悪くなったり、睡眠が浅くなったりする悪影響が生じます。
特に子どもはブルーライトの影響を大人より受けやすく、寝室でのスマホ使用は、睡眠障害リスクを2倍以上に高めるとされています。
具体的な対策としては、次の方法がおすすめです。
- 就寝2時間前にはすべての電子機器を使用終了する
- 夜間はスマホをリビングに置き、寝室には持ち込まない
- ブルーライトカット機能(ナイトモード)を活用する



「スクリーン断ちの時間」を作ることが、深い眠りを引き出す鍵となります。
親自身が生活リズムを整える
子どもは大人の行動パターンを鋭く観察し、自然と真似をします。
特に、就寝・起床のリズムや、夜間の過ごし方は、保護者の影響を強く受けます。
研究では、親自身が規則正しい生活リズムを持っている家庭の子どもほど、睡眠時間が十分に確保され、夜中に目覚める回数も少ないことが示されています。
家庭で実践できるポイントとしては、
- 保護者も夜11時までに就寝する
- 毎朝同じ時間に起床し、朝日を浴びる
- 夜はスマホやパソコンではなく、読書や静かな時間を過ごす



親自身が「睡眠を大切にする姿勢」を見せることが、子どもの睡眠改善への近道です。
参考論文: Parental behaviors and sleep outcomes in infants and toddlers: A review (PMID: 25647667)
睡眠環境を整える
子どもが快適に眠るためには、睡眠環境の整備が欠かせません。
室温、明るさ、音、寝具の快適さなど、周囲の環境は睡眠の質に直結します。
研究では、暗く静かな寝室環境を整えることで、入眠までの時間が短縮され、深い睡眠時間が増えることが示されています。
理想的な環境作りのポイントは、
- 室温は20〜22℃に保つ
- 寝室の照明はオレンジ系の柔らかい光にする
- 防音カーテンや静かなBGMで騒音対策をする
- 通気性の良い寝具を選び、リラックスできる寝床を作る



「眠りやすい環境づくり」が、子どもの自然な入眠を後押しします。
参考論文: Environmental factors associated with sleep in children and adolescents (PMID: 22738658)
子どもにも睡眠の大切さを教える
単に「早く寝なさい」と言うだけでは、子どもは納得しません。
睡眠の重要性を子ども自身が理解し、自発的に睡眠習慣を守る意識を持つことがとても大切です。
研究では、子ども向けに睡眠教育を実施したグループは、睡眠時間が平均30〜45分延び、
さらに日中の集中力や学習意欲が向上する傾向があることが報告されています。
家庭でもできる工夫として、
- 「眠ると脳が元気になる」「背が伸びる」といった具体的メリットを伝える
- 睡眠に関する絵本や動画を一緒に楽しむ
- 毎朝「よく眠れたね」と声かけをして、睡眠へのポジティブな意識を育てる



「なぜ眠ることが大切なのか」を子ども自身が理解すると、自然と睡眠への意識が高まります。
参考論文: Sleep education programs for children and adolescents: A review (PMID: 22850549)
こどもの未来は「9時間睡眠」で変わる
今回は、こどもの理想的な睡眠時間と、科学的根拠に基づく具体的な改善策についてご紹介しました。
睡眠不足は、集中力の低下や感情の不安定化、体の成長や免疫力の低下など、子どもの健やかな発達に深刻な影響を及ぼします。
一方で、毎晩9時間以上の睡眠を確保することで、子どもたちの脳、心、体のすべてがポジティブに成長していくことが最新の研究で明らかになっています。
今日からできる5つの方法──
一貫した就寝ルーティン、電子機器の制限、親自身の生活改善、快適な睡眠環境作り、そして子どもへの睡眠教育──
これらを実践することで、子どもたちの未来は大きく変わります。



まずは、今夜から。
いつもより少し早く、親子で「おやすみなさい」の時間を迎えてみましょう。
「うちの子、運動が苦手かも…」
そんな保護者の声に応えるのが、
三重県松阪市のサンパーク1階『こども運動教室 to JOY(トゥージョイ)』です。


to JOYでは、従来の体操教室やスポーツ少年団ではなく、
こども運動教室to JOYではこどもに合った活用方法が見つかる!
- 苦手な運動が 人目を気にせずに克服できる「パーソナルレッスン」
- きょうだいや友達と一緒に受けられる「グループレッスン」
- 雨・酷暑・ 花粉が 厳しい時期でも自由に遊べる「室内公園」



👉 詳しくはto JOY公式ページ、公式インスタグラム、
申し込みやご質問は公式ラインでお待ちしております。



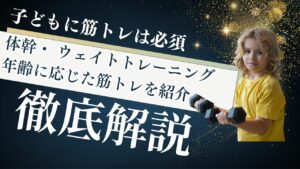


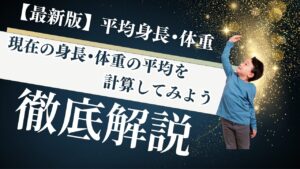

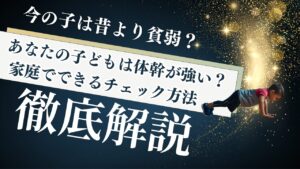
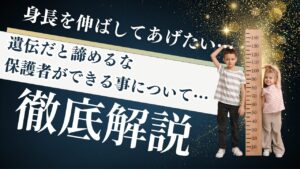
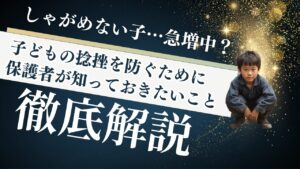
コメント