子どもにプロテインは何歳から?安全性と活用法をわかりやすく解説!
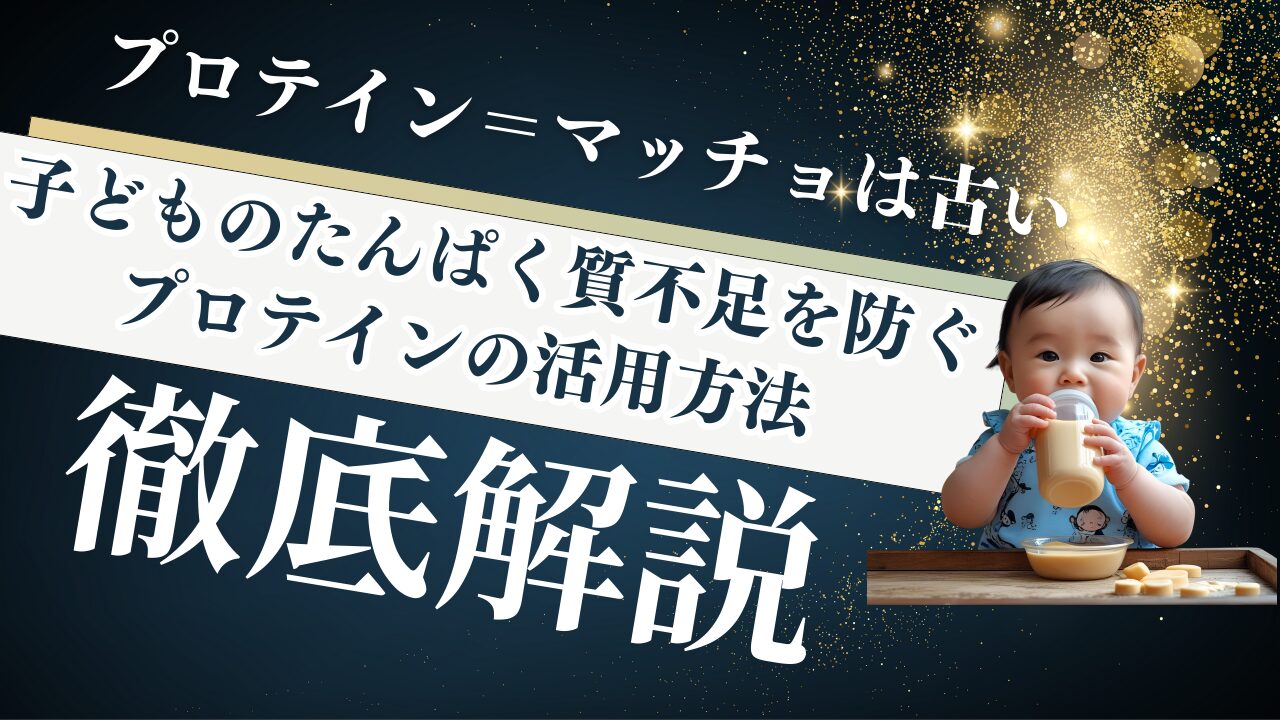
「プロテインって、大人が飲むものじゃないの?」
「成長中の子どもに飲ませても大丈夫?」
そんな不安を感じたことはありませんか?
スポーツを頑張る子や、食が細い子を持つ保護者の間で、最近注目されているのが“プロテイン”です。
でも、「何歳から飲ませていいの?」「体に悪影響はない?」など、わからないことも多く、なかなか手が出せないという声も少なくありません。
この記事では、子どもがプロテインを飲んでも安全なのか、年齢の目安や活用シーン、選び方までをやさしく丁寧に解説します。
読み終える頃には、「わが子に合った取り入れ方」が自然と見えてくるはずです。

片山 拳心(KATAYAMA KENSHIN)
三重県松阪市のサンパーク1階で、こども運動教室to JOY(トゥージョイ)の代表を務めています。
キッズスイミングスクールやフィットネスジムでの指導経験に加え、消防士として多くの現場にも携わってきました。
現在は、消防を退職後に、科学的根拠に基づく安全で楽しい運動教室を開業。
保有資格
- 運動遊び実践サブリーダー(NPO運動保育士会)
- 子育て脳機能アドバイザー/ディレクター
- 幼児運動遊び実践アシスタント
- キッズコーディネーショントレーナー(KCT)
- (一社)スポーツリズムトレーニング協会認定
・ アドバンスドディフューザー(AD)
・ リズムステップディフューザー(DF)
子どもがプロテインを飲んでも大丈夫?基本の疑問を解決
「子どもにプロテインって、そもそも必要なの?」
「まだ小さいのに、体に負担じゃないの?」
そんな不安を感じている保護者の方も多いはずです。
この章では、プロテインの基本的な役割や、子どもにとって必要な理由、年齢の目安や注意点について、やさしく解説していきます。
まずは、そもそもプロテインとはどんなものなのか?そして、成長期の子どもになぜ注目されているのか?という点から見ていきましょう。
プロテインとは?子どもに必要な理由
「プロテイン=筋肉をつけるための飲み物」というイメージが強いかもしれませんが、日本語訳で「たんぱく質」です。
牛乳や大豆などから抽出されたたんぱく質を主成分とし、成長や体づくりに役立つ栄養補助食品として活用されています。
子ども向けに作られた“ジュニアプロテイン”は、大人用とは違い、たんぱく質は控えめに、カルシウムや鉄分、ビタミンなどの栄養素を強化しているのが特徴です。
成長期の子どもは、大人と比べて基礎代謝が高く、運動量も多く、体をつくるための栄養が多く必要になります。
とくにスポーツをしている子は、通常よりも1.5〜2倍のたんぱく質が必要になることもあるとされ、体力面のサポートが求められます。
また、少食でごはんをあまり食べられない子や、偏食があって栄養が偏りがちな子にとって、プロテインは食事では足りない部分を補う“栄養のサポート役”として使える点でも注目されています。
何歳からプロテインを飲ませてもいいの?
プロテインは医薬品ではなく食品に分類されるため、「この年齢から」といった厳密な決まりはありません。
しかし、一般的には小学校高学年(10歳頃)以降からの摂取が目安とされることが多く、体の発達状況や食事内容によって判断されます。
最も大切なのは、ふだんの食事でしっかり栄養が取れているかを確認したうえで、補助的に活用するかどうかを判断すること。
食事が十分であればプロテインに頼る必要はなく、逆に不足している場合は、体に負担をかけない範囲で補っていくという姿勢が大切です。
身長や体への悪影響はある?
「プロテインを飲むと身長が伸びなくなるのでは?」という不安を耳にすることがあります。
ですが、そのような根拠はありません。
プロテインはあくまで「たんぱく質を効率よく補う手段」であり、筋肉の材料となる栄養素のひとつです。
プロテインを飲んだからといって、筋肉質になったり、成長が止まったりすることはありません。
身長の伸びには、遺伝・睡眠・運動・栄養のバランスが影響しており、プロテイン単独での影響は限定的です。
 片山 拳心
片山 拳心プロテインは薬ではありません。たんぱく質を英語にしただけの言葉です。
“お肉を食べると成長が止まる”と言っているのと同じことなので、意味合いには注意が必要です。
ただし、注意したいのは過剰摂取による内臓への負担です。
たんぱく質を摂りすぎると、肝臓や腎臓に負担がかかり、腹痛や下痢、発熱など体調不良の原因になることがあります。
特に成長中の子どもには、体重1kgあたり2.0gを超えるたんぱく質摂取は避けたほうがよいとされています。
また、市販のプロテイン製品の中には、人工甘味料や香料、保存料などが添加されているものもあるため、
体質によってはアレルギー反応や体調への影響が出るケースもあります。



昔のプロテインは正直、美味しくなかったです。でも今は、人工甘味料などの工夫でかなり飲みやすくなりました。
“人工甘味料”と聞くと不安になりますが、食品に使われる量はごくわずかです。このテーマについても、今後別の記事で詳しくご紹介しますね。
こんなときはプロテインが役立つ|活用シーンと注意点
「プロテインってアスリート向けでしょ?」
そう思っていた保護者の方も、近年では子ども用のプロテインを見かけることが増えて、興味を持ち始めたのではないでしょうか。
でも、どんなタイミングで使うべきか、どのような子どもに合っているのかは意外とわかりづらいものです。
この章では、子どもの成長や生活のなかで、プロテインが役立つシーンを具体的に解説していきます。
スポーツをしている子どもの栄養補給に
成長期の子どもがスポーツに取り組むと、体への負荷は思っている以上に大きくなります。
とくに部活動やクラブチームに所属している子どもは、日々の練習で筋肉や体力を消耗しやすく、回復のための栄養補給が欠かせません。
そこで役立つのがプロテインです。夜遅くまで練習がある子や、食事が不規則になりがちな家庭では、プロテインをうまく取り入れることで、必要な栄養を無理なく補うことができます。
ジュニア用のプロテインなら、たんぱく質のほかにカルシウムやビタミンも一緒に補える設計になっているので、成長を支えるサポート飲料として活用しやすいでしょう。
食が細い・偏食気味の子の栄養サポートに
幼児期〜小学校低学年の時期は、食べる量が安定しない・好き嫌いが多いといった傾向があり、十分な栄養を毎日の食事だけで補うのが難しいケースもあります。
そこで役立つのが、補助的に使えるジュニアプロテインです。
少量でもたんぱく質やカルシウム、鉄分などの重要な栄養素を補うことが可能です。
間食として取り入れることで、食事で足りない栄養を補える“補食”として活用でき、子どもの成長をやさしく支える手段のひとつになります。



特に朝食は、たんぱく質が不足しがちです。
シリアルに牛乳で割ったプロテインをかけてあげるだけで、かなり栄養バランスのよい朝食になりますよ。
食事が不十分なときの補助として
忙しい平日の朝や、時間がない夕食時など、毎回きちんとした栄養バランスのある食事を用意するのは簡単なことではありません。また、子どもが体調を崩していたり、食欲が落ちていたりする時期も、必要な栄養を食事だけでまかなうのが難しい場面があります。
そんなとき、プロテインは補助食品として活用できます。
とくに、お菓子やジュースの代わりにプロテインを“補食”として取り入れることで、
小腹を満たしながらも、たんぱく質・カルシウム・鉄分などを効率よく補うことができます。
その結果、食事で摂りきれなかった栄養素を補完しやすくなります。
「食べさせなきゃ」と思うほどプレッシャーを感じる保護者も少なくありません。
そんなときこそ、無理せず栄養を補える手段のひとつとして、プロテインを活用するのも選択肢です。



アイスクリームとプロテインをミキサーで混ぜるだけでも、栄養価がぐんとアップします。
ただのデザートを“ちょっといい補食”に変えるだけで、日常に取り入れやすくなりますよ。
与えるときに気をつけたいこと
プロテインはあくまで「栄養補助食品」であり、基本はあくまでも食事が中心という考え方が大切です。
食事には、栄養の摂取だけでなく、「噛むこと」によるあごの発達や、「座って食べる」という生活習慣の形成といった、成長に欠かせない要素も含まれています。
そのうえで、プロテインを活用する際には以下の点に注意しましょう。
• 過剰摂取に注意すること
体重1kgあたり2.0gを超えるたんぱく質摂取は、腎臓や肝臓に負担をかけるおそれがあります。
• アレルギー体質に配慮すること
牛乳アレルギーがある場合はホエイプロテインを避け、大豆を原料としたソイプロテインなどを検討しましょう。
• 少量から始めて様子を見ること
いきなりたくさん飲ませるのではなく、まずは少量からスタートし、体調の変化がないかを確認することが大切です。
• 体調不良時はすぐに中止し、医師に相談を
下痢や腹痛、発疹などの症状が見られた場合は摂取をやめ、医師や管理栄養士に相談しましょう。
子どもの体はとても繊細です。
安全に活用するためにも、保護者が正しい情報を持ち、少しずつ丁寧に取り入れていくことが大切です。
子ども向けプロテインの選び方とおすすめ商品
「プロテイン」とひとことで言っても、商品ごとに栄養バランスや味、対象年齢などが大きく異なります。
子どもの体に合ったものを選ぶためには、ジュニア用と大人用の違いや、成分のチェックポイントを知っておくことが大切です。
この章では、安全性や飲みやすさ、続けやすさを軸に、それぞれの特徴をわかりやすくまとめていきます。
ジュニア用と大人用はどう違う?
プロテインには「ジュニア用」と「大人用」がありますが、実際のところ成分の大きな違いは、たんぱく質の量と栄養素の追加有無です。
ジュニア用は、子どもの発育に合わせてたんぱく質は控えめに、カルシウムや鉄、ビタミン類などを強化してあるのが特徴です。
ここで気をつけたいのが、価格の違いです。
ジュニア用は「子ども専用」として付加価値がついている分、大人用より割高になることが多く、
たとえば「味」「ビタミン添加」「見た目のやさしさ」などが価格に反映されている場合もあります。
ですが、同じ原材料(ホエイやソイ)を使っていれば、大人用のプロテインを1杯(半量程度)に減らすことで、実質的にはジュニア用とほぼ同じです。
成分表示を確認したうえで調整すれば、特別に子ども専用品を用意しなくても問題ない場合もあります。
とくに、保護者自身もプロテインを飲んでいるご家庭では、わざわざ分けて購入しなくても兼用できることがあるという点は、知っておくと便利です。



ジュニア用には、“ベースボール用プロテイン”のような名前の商品もありますが、
それ自体に特別な根拠があるわけではなく、ブランド名として付けられているだけの場合も多いです。
価格に惑わされず、自分たちに合ったプロテインを選びましょう。
安全性・味・栄養バランスで選ぶ
子どもにプロテインを与えるときに、最も大切にしたいのが「安全性」と「続けやすさ」です。
とくに成長期の体は繊細なので、添加物の有無や栄養の偏りには十分に注意が必要です。
つぎに、続けやすさの面では、「味」の工夫も大切です。
子どもが無理なく飲めるよう、ココア・バナナ・イチゴなどのフレーバーが用意された製品も多く、
牛乳や豆乳に混ぜると自然な甘みになり、毎日の習慣に取り入れやすくなります。
また、栄養バランスも製品選びのポイントです。
たとえば、カルシウム・マグネシウム・亜鉛・ビタミンD・ビタミンB群など、
たんぱく質以外の栄養素もバランスよく含まれている商品であれば、食事で不足しがちな微量栄養素を一緒に補えます。
「安心して続けられるかどうか」を重視して、家庭のニーズに合ったプロテインを選ぶようにしましょう。
プロテインを味方にして、成長をやさしく支えよう
今回は、「子どもにプロテインは何歳から飲ませてよいのか?」という疑問を中心に、
その安全性や活用シーン、選び方について解説しました。
- プロテインはあくまで「たんぱく質」であり、食事だけで補いきれない栄養を助ける補助食品であること
- 10歳前後を目安に、食事の状況に応じて少量から検討するのが一般的であること
- スポーツ・偏食・食の細さなど、さまざまな場面でプロテインが役立つこと
- 子ども専用品だけでなく、大人用を調整して使う方法もあること
子どもの成長を支える手段の一つとして、プロテインを「正しく、無理なく」取り入れることができれば、
毎日の食事づくりや健康管理の負担も少し軽くなるはずです。
まずは少量から試して、家庭のスタイルに合うかどうかを確認してみてはいかがでしょうか。
\ かたやま代表の子育てお役立てコラム /
-


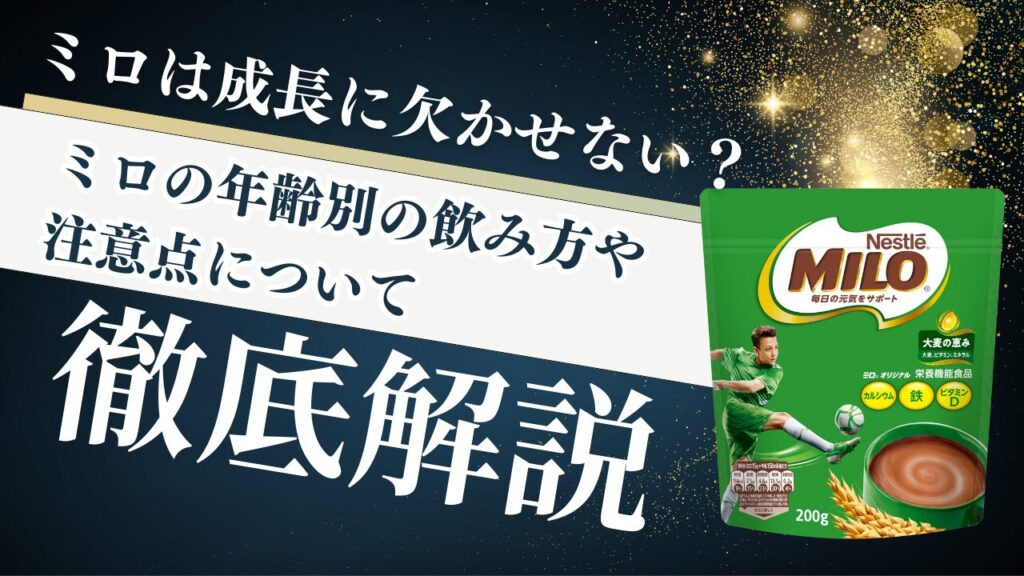
ミロは何歳から飲める?子どもの成長と女性におすすめな理由も解説
「ミロって何歳から飲ませても大丈夫?」 「栄養はあるけど糖分が心配…」 そんな疑問を持つ保護者の方も多いのではないでしょうか。 ミロは何歳から飲むことができる… -



プロ監修!子どものプレゼントに最適な自宅用ソフト跳び箱おすすめ【3選】
「最近ゲームばかりで、ぜんぜん体を動かしてないな…」 「プレゼントするなら、運動神経の向上に役に立つものにしたい」 そんなふうに思ったことはありませんか? この… -



運動神経が悪い子どもの特徴とは?専門家が家庭でできる伸ばし方も解説
「うちの子、運動神経が悪いのかも…」 「周りの子と比べて動きがぎこちない気がする」 そんなふうに悩んでいる保護者の方は、決して少なくありません。 実際、子どもの…
「うちの子、運動が苦手かも…」
そんな保護者の声に応えるのが、
三重県松阪市のサンパーク1階『こども運動教室 to JOY(トゥージョイ)』です。


to JOYでは、従来の体操教室やスポーツ少年団ではなく、
こども運動教室to JOYではこどもに合った活用方法が見つかる!
- 苦手な運動が 人目を気にせずに克服できる「パーソナルレッスン」
- きょうだいや友達と一緒に受けられる「グループレッスン」
- 雨・酷暑・ 花粉が 厳しい時期でも自由に遊べる「室内公園」



👉 詳しくはto JOY公式ページ、公式インスタグラム、
申し込みやご質問は公式ラインでお待ちしております。



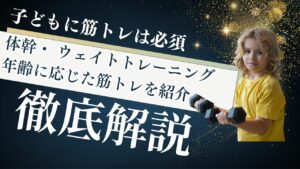


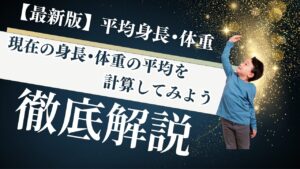

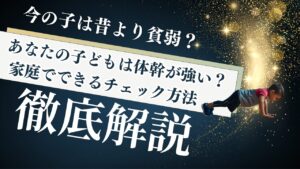
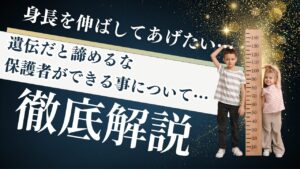
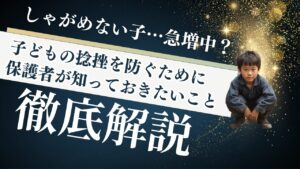
コメント