いま注目の「マルチスポーツ」とは?子どもが複数のスポーツを経験する意味
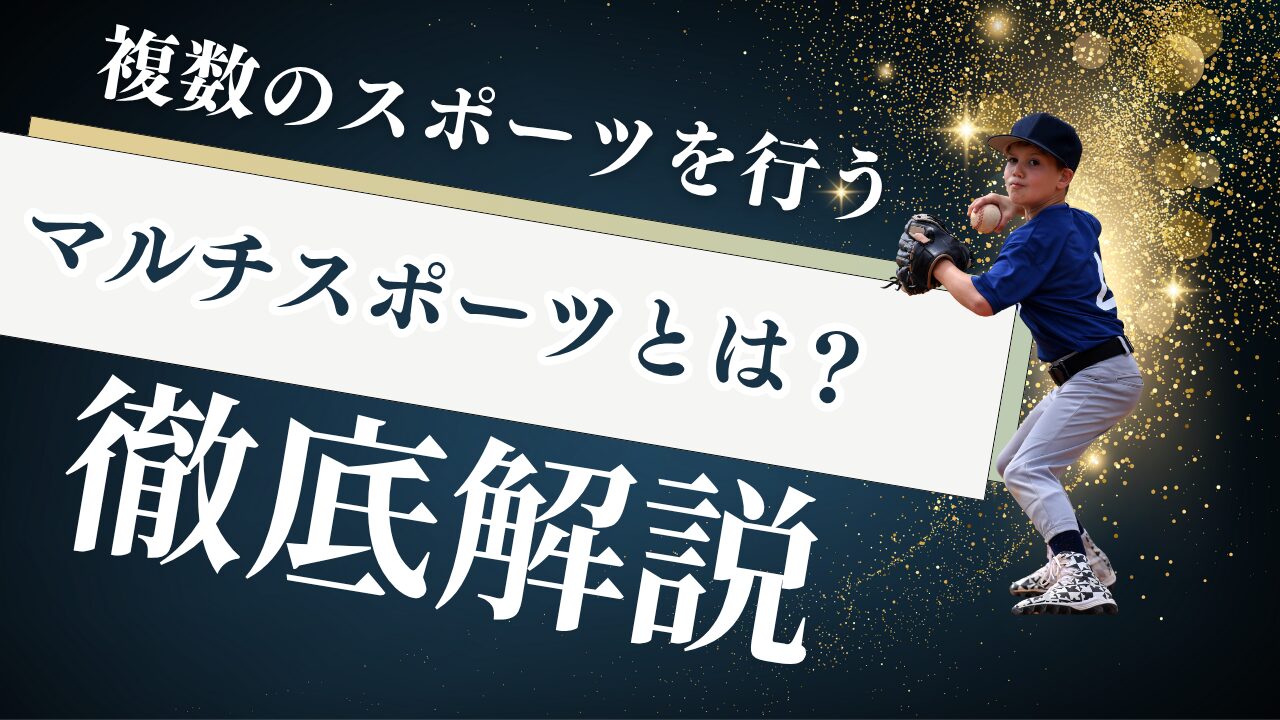
「ひとつのスポーツだけじゃなく、いろんな運動を体験させたい」
そんな思いを持ったことはありませんか?
今、スポーツ庁が動き出し、子どもたちに複数のスポーツを経験させる「マルチスポーツ」が注目されています。
運動能力を伸ばすだけでなく、心や社会性を育て、将来の選択肢も広げてくれる新しいスポーツのかたちです。
本記事では、マルチスポーツの意味や効果、日本の最新の取り組み、
そして、to JOY運動教室のように身近で実践されている事例まで、わかりやすくご紹介します。

片山 拳心(KATAYAMA KENSHIN)
三重県松阪市のサンパーク1階で、こども運動教室to JOY(トゥージョイ)の代表を務めています。
キッズスイミングスクールやフィットネスジムでの指導経験に加え、消防士として多くの現場にも携わってきました。
現在は、消防を退職後に、科学的根拠に基づく安全で楽しい運動教室を開業。
保有資格
- 運動遊び実践サブリーダー(NPO運動保育士会)
- 子育て脳機能アドバイザー/ディレクター
- 幼児運動遊び実践アシスタント
- キッズコーディネーショントレーナー(KCT)
- (一社)スポーツリズムトレーニング協会認定
・ アドバンスドディフューザー(AD)
・ リズムステップディフューザー(DF)
マルチスポーツってなに?その基本と注目される理由
「マルチスポーツ」という言葉を耳にしたことはありますか?
これは、こどもが複数のスポーツを同時期に楽しむことを意味します。
たとえば、サッカーと水泳、体操とダンスなど、異なる動きを持つスポーツを組み合わせて取り組むことで、
偏りのない体の使い方が身につき、楽しみながら運動能力を伸ばせる点が特徴です。
今、このマルチスポーツに注目しているのが「スポーツ庁」です。
2024年からは、子どもたちのスポーツ環境を見直すべく、
「日本型マルチスポーツ」の構築に向けた本格的な取り組みが始まっています。
背景にあるのは、日本ではまだひとつの競技に専念する傾向が強いこと。
しかし、海外ではマルチスポーツは当たり前の考え方となっており、
たとえばアメリカでは約8割の中高生が複数のスポーツを経験しているというデータもあります。
スポーツ庁が主導し、大学や地域と連携しながら環境づくりを進めている今、
私たち保護者にも「マルチスポーツってどんなもの?どんな良さがあるの?」と知っておく価値があります。
次の章では、こどもの成長にどんな影響があるのかを詳しく見ていきましょう。
マルチスポーツとは子どもにとってどんな活動?
マルチスポーツとは、ひとつの競技だけでなく、複数のスポーツを同時期に体験することを指します。
たとえば、週に1回はサッカー、別の日には体操や水泳など、違う種目に触れるスタイルです。
この活動の大きな魅力は、さまざまな動きやルールに触れることで、
こどもの体の発達だけでなく、考える力や協調性も自然に育まれる点にあります。
また、スポーツごとに関わる仲間や指導者が変わることで、
人間関係やコミュニケーションの幅も広がります。
 片山 拳心
片山 拳心「走る」「投げる」「飛ぶ」「バランスをとる」など、色々な動きを取り入れることができるんです。
競技の枠にとらわれず、「運動そのものが楽しい」「身体を動かすって面白い」という感覚を育てるのが、マルチスポーツの原点です。
運動能力だけじゃない、社会性や心の成長への効果
マルチスポーツの魅力は、運動能力の向上だけにとどまりません。
実は、こどもの心の成長や社会性の発達にも、大きな意味があるのです。
複数のスポーツに取り組むことで、
こどもはそれぞれの場面で異なるルールや仲間に触れます。
- 初めてのことに挑戦する勇気
- 新しい友達との関わり方
- 困ったときに相談する力
など、スポーツを通じた“生きる力”が少しずつ育っていきます。



「この前のチームとはやり方が違う」そんな気づきも、こどもにとって大きな学びになります。
また、同じ競技を続けていると気づきにくい“自分の得意・不得意”を見つける機会にもなります。
「このスポーツは楽しい」「こっちは少し苦手かも」と感じることも、
こどもが自分を知る大切な一歩です。
日本と海外での取り組みの違いとは
マルチスポーツという考え方、実は海外ではごく当たり前のこととして根づいています。
たとえばアメリカでは、学校の部活動に「シーズン制」が取り入れられており、
春は陸上、秋はサッカー、冬はバスケットボールといったように、
年間を通してさまざまなスポーツに取り組む環境が整っています。
また、スペインの一部地域では、12歳までは特定の競技での選手登録を禁止し、
多種目に触れることを奨励しているケースもあります。
一方、日本では「ひとつの習い事を長く続けることが大事」とされる文化が強く、
複数のスポーツに並行して取り組める環境は、まだまだ限られています。
| 海外(アメリカ・スペインなど) | 日本 | |
|---|---|---|
| 一般的なスタイル | 複数のスポーツを季節ごとに切り替えて楽しむ | 一つの競技を継続的に行うのが主流 |
| 教育との関係 | 学校教育の一環としてスポーツが組み込まれる | 習い事やクラブ活動として個別に行うケースが多い |
| 選手育成の考え方 | 幅広い運動経験から適性を見極める | 早期から専門競技に集中する傾向 |
| 制度の例 | スペインの一部では12歳までの競技登録を禁止 | 特に制限はなく、早くから単一競技に取り組む場合も |



「やるなら一つに絞って本気でやらないと」という風潮、まだ残っていますよね。
しかし今、日本でもその流れが少しずつ変わろうとしています。
スポーツ庁をはじめとする国の機関や大学が中心となって、
マルチスポーツの価値や可能性を見直す取り組みが始まっているのです。
いま進む「日本型マルチスポーツ」の推進と期待
これまで日本では、ひとつのスポーツにじっくり取り組むスタイルが一般的でした。
でも今、その流れに大きな変化が生まれようとしています。
その中心にあるのが、「スポーツ庁」の取り組みです。
2024年度から、本格的に日本型マルチスポーツ環境の整備に乗り出しました。
この取り組みは、筑波大学との連携のもとで行われており、
調査研究だけでなく、実際の体験イベントや教材づくりなど、実践的な活動が進んでいます。
背景にあるのは、「すべてのこどもに、もっと自由にスポーツを楽しんでほしい」という思いです。
マルチスポーツは、アスリート育成のためだけではありません。
- こどもがスポーツを好きになること
- 運動の苦手意識を持たずにすむこと
- 仲間と関わる力を育てること
こうした“スポーツとのいい出会い”を増やすための、大切な一歩として期待されています。
スポーツ庁が目指すマルチスポーツの環境づくり
「マルチスポーツをもっと日本にも広めたい」
そんな思いから、スポーツ庁は2024年度より本格的な事業をスタートさせました。
その名も、「地域における子供たちの多様なスポーツ機会創出支援事業」。
この事業では、以下のような取り組みが進められています。
- 国内外のマルチスポーツの先進事例や研究の調査
- スポーツ団体と連携した体験イベントの開催
- 子ども向けのトレーニング動画などの教材づくり
さらにこの事業は、筑波大学に委託され、教育・研究・実践の3つをつなぐ動きとして全国的に展開されています。



国が本腰を入れて進めていること、あまり知られていないかもしれませんね。
スポーツ庁はこの活動を通して、日本の地域ごとに合った「日本型マルチスポーツ」の形を見つけ出し、
すべてのこどもがスポーツと出会い、楽しめる社会づくりを目指しています。
子どもたちが楽しみながら成長できる場とは
マルチスポーツが目指すのは、「運動能力の高い子」をつくることだけではありません。
もっと大切にしているのは、こどもが心からスポーツを楽しむこと、そして体を動かすことが好きになることです。
一つの競技に縛られず、いろんなスポーツを試せる環境は、
こどもにとって「好き」「楽しい」を見つけるきっかけになります。
また、競争よりも体験や仲間との関わりを重視することで、
安心してチャレンジできる空気が生まれます。



まずは「やってみたい」と思えること。それが成長の第一歩になります。
スポーツ庁や筑波大学が実施している取り組みの多くが、
この“楽しさ”を中心に据えているのは、そうした理由があるからです。
今後、地域でもマルチスポーツ型の教室やイベントが広がっていけば、
運動が苦手な子でも「これなら楽しい」と感じられる場が増えていくはずです。
マルチスポーツで子どもの可能性をひろげよう
本記事では、こどもが複数のスポーツを体験する「マルチスポーツ」の意義や効果、そして日本での最新の取り組みをご紹介しました。こうした動きを受けて、松阪市にあるこども運動教室to JOYも、実はマルチスポーツ的な環境を提供している教室のひとつです 。
to JOY運動教室では、跳び箱・鉄棒・なわとび・側転など、体操だけでなく多種多様な運動を遊び感覚で取り入れています。固定の競技ではなく、運動の土台となる多様な動きを通じて「動ける体」を育むことを目指しています 。
また、グループレッスンとパーソナルレッスンを組み合わせた形式で、
- 苦手な運動を人目を気にせずに克服できるパーソナルサポート
- 仲間とともに楽しみながら挑戦できるグループ体験
という二本柱で、子ども一人ひとりの成長を支えています。
このようにto JOY運動教室は、「複数の動きを楽しく体験する」という点で、マルチスポーツの魅力と効果を日常のレッスンに取り入れています。スポーツ庁や筑波大学が掲げる理念を地域で実践している、まさに“日本型マルチスポーツ教室”のモデルと言えるでしょう。
こどもにとってのマルチスポーツは、
- 身体の偏りを防ぎ
- 自分の得意・不得意に気づき
- 運動を楽しむ気持ちが続く
ことにつながります。
to JOY運動教室のように、遊びと学びが交差する空間を通じて、
「運動って楽しい」「やってみたい」と思う種が芽生える。
そんな環境が広がっていくことが、こどもの未来にとって大きな力になるはずです。
「うちの子、運動が苦手かも…」
そんな保護者の声に応えるのが、
三重県松阪市のサンパーク1階『こども運動教室 to JOY(トゥージョイ)』です。


to JOYでは、従来の体操教室やスポーツ少年団ではなく、
こども運動教室to JOYではこどもに合った活用方法が見つかる!
- 苦手な運動が 人目を気にせずに克服できる「パーソナルレッスン」
- きょうだいや友達と一緒に受けられる「グループレッスン」
- 雨・酷暑・ 花粉が 厳しい時期でも自由に遊べる「室内公園」



👉 詳しくはto JOY公式ページ、公式インスタグラム、
申し込みやご質問は公式ラインでお待ちしております。

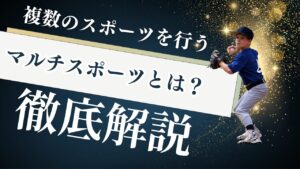

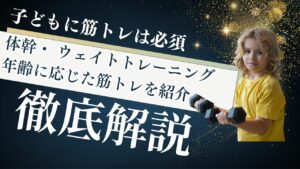


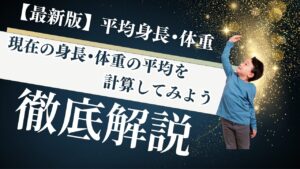

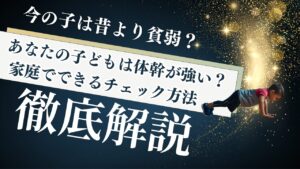
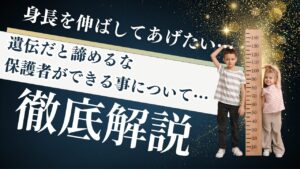
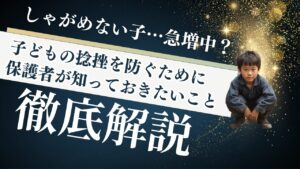
コメント