勉強ができる子はよく遊ぶ?有酸素運動が子どもの学力に与える影響とは
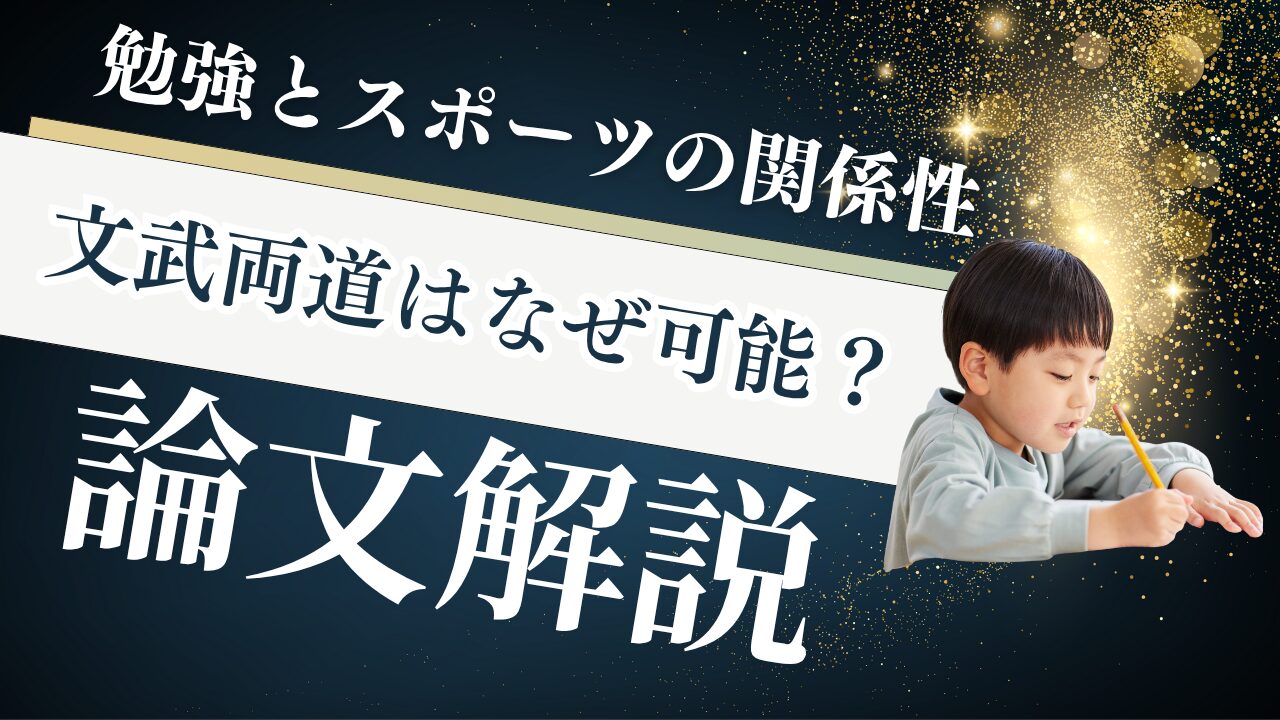
「うちの子、どうしても勉強に集中できなくて…」
「がんばっているのに、なかなか成績が伸びない…」
そんなお悩みをお持ちの保護者の方に、ぜひ知っていただきたいのが、“体を動かすこと”と“学力”の意外な関係です。
近年の研究では、軽く息が上がるような運動をすることで、子どもの集中力・記憶力・考える力といった“学ぶ土台”が整いやすくなることが分かってきました。
この記事では、脳科学や教育の研究をもとに、運動と学力のつながりをわかりやすく解説します。
読み終えたときには、「今日からできること」がきっと見つかるはずです。
お子さんの学びを応援する新しい視点として、ぜひ参考にしてみてください。

片山 拳心(KATAYAMA KENSHIN)
三重県松阪市のサンパーク1階で、こども運動教室to JOY(トゥージョイ)の代表を務めています。
キッズスイミングスクールやフィットネスジムでの指導経験に加え、消防士として多くの現場にも携わってきました。
現在は、消防を退職後に、科学的根拠に基づく安全で楽しい運動教室を開業。
保有資格
- 運動遊び実践サブリーダー(NPO運動保育士会)
- 子育て脳機能アドバイザー/ディレクター
- 幼児運動遊び実践アシスタント
- キッズコーディネーショントレーナー(KCT)
- (一社)スポーツリズムトレーニング協会認定
・ アドバンスドディフューザー(AD)
・ リズムステップディフューザー(DF)
なぜ運動が“頭のよさ”につながるの?
「運動すると頭が良くなる」——そんな話を聞いたことはありませんか?
実はこれ、単なる噂ではありません。
子どもが適度な運動を続けることで、集中力・記憶力・考える力といった“学ぶための力”が育ちやすくなるという研究結果が数多く報告されています。

とくに効果が期待できるのが、ジョギングやウォーキング、なわとびのような「有酸素運動」です。
体を動かすことで脳に酸素や栄養が送られ、神経が活性化し、勉強への集中がしやすくなるといわれています。
それでは本章では、運動が脳にどのような影響を与え、どうして“勉強ができる子”につながるのかについて、もう少し詳しく見ていきましょう。

運動すると脳の働きがよくなる理由
子どもが体を動かすと、「頭がスッキリした」「気持ちが落ち着いた」と感じることはありませんか?
これは実際に、脳の中で良い変化が起きているサインです。
たとえばジョギングやなわとびなどの息が上がるような運動をすると、心拍数が上がり、脳にも多くの血液が流れ込むようになります。
その結果、酸素や栄養が脳のすみずみにまで届き、神経細胞が活発に働く状態がつくられます。
特に活性化されるのが、「前頭前野(ぜんとうぜんや)」という、脳の前側にある領域です。
ここは、集中力・思考力・感情のコントロールなど、“学ぶ力”を支える重要な場所です。
この前頭前野の発達がゆっくりな子は、落ち着いて話を聞くことが苦手だったり、気持ちの切り替えがうまくできなかったりする傾向があります。
そんな子どもにとっても、息が上がるような運動は、脳の発達を促す後押しになるのです。
 片山 拳心
片山 拳心運動中に分泌される「BDNF(脳由来神経栄養因子)」は、神経細胞の成長を助ける“脳の栄養”のような物質です。記憶や学習に欠かせない、重要な役割を果たしますよ。
引用論文
1. Cotman CW, Berchtold NC (2002)
「Exercise: a behavioral intervention to enhance brain health and plasticity」
• 内容:運動が脳の可塑性やBDNF分泌に与える影響を検討
• 方法:ラットに週5回、各60分のトレッドミル運動を8週間実施
• 結果:BDNFの分泌量が最大で200%(2倍)に増加
• URL:https://doi.org/10.1016/S0166-2236(02)02143-4
集中力や記憶力を育てる“脳のスイッチ”
息が上がるような運動には、子どもの集中力や記憶力を引き出すスイッチのような働きがあります。
この働きを支えているのが、海馬という脳の奥にある部位です。
海馬は最近、記憶に関する話題で耳にしたことがある方も多いかもしれません。
この部分は、新しいことを覚えたり、必要な情報を思い出したりする、いわば記憶の中枢として知られています。
そしてこの海馬も、息が上がるような運動によって活性化されることがわかっています。
たとえば、リズムよくジャンプしたり、一定時間しっかり歩いたりするような動きが、海馬の神経活動を刺激し、記憶の定着を助けると言われています。



海馬は“覚える力”を支える場所。だから、遊びの中でもしっかり体を動かすことが、学ぶ力につながっていくんですよ。
さらに、体を動かすことで気分が安定しやすくなることも大きなポイントです。
ストレスを感じているとき、脳は本来の力を発揮しにくくなりますが、運動をすることでストレスホルモンが減り、集中しやすい心の状態がつくられます。
つまり、息が上がるような運動は、脳が働きやすい状態と、気持ちが落ち着いた状態を同時に整えてくれる、大切なスイッチなのです。
実際にわかった!運動と勉強の関係
ここまで、運動が脳に良い影響を与える理由についてご紹介してきました。
では実際に、運動をしている子どもたちは、どれほど学力にも良い変化が見られるのでしょうか。
この疑問に答えてくれるのが、国内外のさまざまな研究です。
子どもたちに運動を取り入れたグループとそうでないグループを比較し、テストの成績や集中力にどんな違いが出たのかを調べた結果が多数発表されています。
それでは本章では、実際の研究結果から、運動と勉強のつながりについて具体的に見ていきましょう。


たった20分のウォーキングで計算力アップ!?
アメリカで行われた研究により、息が上がるような運動が、子どもの学力にプラスの影響を与えることがわかっています。
この研究では、小学3年生から5年生の子どもたちを対象に、ある実験が行われました。
内容はとてもシンプルで、「20分間ウォーキングをしたあとに、読解力や計算力を測るテストを行う」というものです。
結果は驚くべきものでした。
運動をしたグループの子どもたちは、そうでないグループに比べて、テスト中の集中力が高まり、正答率が明らかに上昇したのです。
この実験は、授業の前や勉強の前に軽く体を動かすだけでも、脳が働きやすい状態になることを証明した例として注目されています。
運動は長時間する必要はありません。
ほんの少しのウォーキングや軽いジャンプでも、子どもの“やる気スイッチ”を入れる手助けになることがわかっています。
引用論文
1. Hillman CH et al. (2009)
「The effect of acute treadmill walking on cognitive control and academic achievement in children」
• 内容:小学3〜5年生に対し、運動直後の学力テスト結果を分析
• 方法:20分間のトレッドミルウォーキングを実施し、その直後に読解・計算テストを実施
• 結果:運動後のグループは集中力・反応速度・正答率ともに向上
• URL:https://doi.org/10.1016/j.neuro.2009.05.001
長く続けるほど学力もアップしやすい
短時間の運動でも学力に良い変化が見られることは分かっていますが、運動を長く続けることで、その効果はさらに高まるという研究もあります。
2016年に発表された大規模なレビュー研究では、これまでに行われた58件の論文をもとに、運動と学力の関係を分析しました。
対象は小学生から高校生までの子どもたちです。
その結果、定期的に運動をしている子どもたちは、集中力や思考力が高く、学業成績も良い傾向にあることが明らかになりました。
とくに週に数回以上、継続して運動に取り組んでいる子どもほど、テストの点数や問題解決力に良い影響が出ていたと報告されています。
これは、体を動かすことで脳がよく働く状態が習慣として定着し、学ぶための準備が日常的に整っていることを意味しています。



幼いころから運動を習慣にすると、自然と体を動かすことが好きな子に育ちますよ。to JOYでは“楽しい”から始めて、学びにつながる体づくりをサポートしています。
子どもにとって、学力を高めるために特別な勉強法を探すよりも、まずは生活の中に運動を取り入れることが、一番の近道になるかもしれません。
引用論文
2. Donnelly JE et al. (2016)
「Physical Activity, Fitness, Cognitive Function, and Academic Achievement in Children: A Systematic Review」
• 内容:運動と学業成績・認知機能の関係について58研究をまとめたレビュー
• 方法:観察研究・介入研究を含む複数の論文を分析
• 結果:定期的な運動が集中力・記憶力・学業成績の向上に関連していると結論づけられた
• URL:https://doi.org/10.1249/MSS.0000000000000901
読む力・考える力にもいい影響が
息が上がるような運動は、計算や記憶だけでなく、読む力や考える力にも良い影響を与えることがわかっています。
スペインで行われた大規模な分析では、運動と学力の関係について92件の研究をまとめ、特に読解力や論理的思考力に注目しました。
その結果、継続的に体を動かしている子どもたちは、読み取りの精度やスピード、文章の理解力などが高い傾向にあることが明らかになっています。
また、論理的に物事を考える力や、難しい課題に粘り強く取り組む姿勢にも、運動の習慣が影響しているとされています。
文章を読んで意味をつかむ力や、自分の考えをまとめて表現する力は、すべての教科の土台になります。
だからこそ、運動で集中しやすい脳と前向きな気持ちを育てることが、勉強全体を支える“見えない準備”につながるのです。
引用論文
3. Álvarez-Bueno C et al. (2017)
「Academic Achievement and Physical Activity: A Meta-analysis」
• 内容:運動と学力の関係を調べた92研究のメタ分析
• 方法:幼児から高校生までの複数の研究データを統合して分析
• 結果:特に読解力と数学力に対して、継続的な運動が明確なプラス効果を示した
• URL:https://doi.org/10.1016/j.pmedr.2017.03.005
勉強が苦手な子ほど“体を動かす習慣”を
今回は、運動と学力の関係について、脳の働きや実際の研究結果をもとにご紹介しました。
息が上がるような運動をすると、集中力や記憶力、思考力を支える脳の領域が活性化し、勉強に取り組みやすい状態が自然と整っていきます。
また、前向きな気持ちや粘り強さといった、学びに必要な“心の力”を育てるうえでも、運動はとても大切な土台になります。
勉強に苦手意識がある子や、集中が続かない子ほど、まずは体をしっかり動かすことから始めてみるのがおすすめです。
家庭では、朝のウォーキングや遊びの中のジャンプ運動など、無理なくできることから少しずつ取り入れてみましょう。
そして、もっと運動を楽しく習慣化したいと思ったときは、私たちto JOYのような運動教室も、きっと力になれるはずです。
「うちの子、運動が苦手かも…」
そんな保護者の声に応えるのが、
三重県松阪市のサンパーク1階『こども運動教室 to JOY(トゥージョイ)』です。


to JOYでは、従来の体操教室やスポーツ少年団ではなく、
こども運動教室to JOYではこどもに合った活用方法が見つかる!
- 苦手な運動が 人目を気にせずに克服できる「パーソナルレッスン」
- きょうだいや友達と一緒に受けられる「グループレッスン」
- 雨・酷暑・ 花粉が 厳しい時期でも自由に遊べる「室内公園」



👉 詳しくはto JOY公式ページ、公式インスタグラム、
申し込みやご質問は公式ラインでお待ちしております。

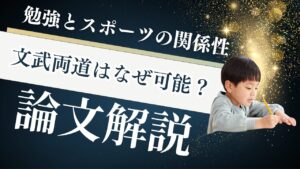

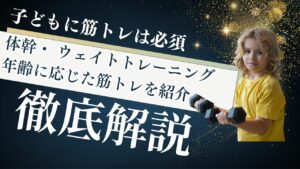


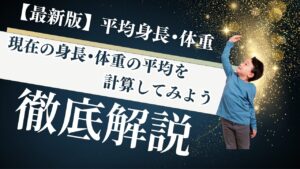

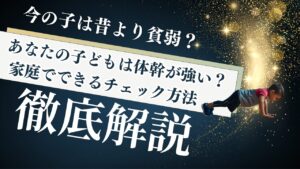
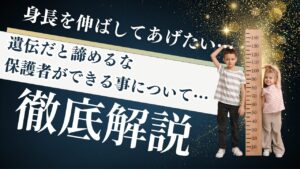
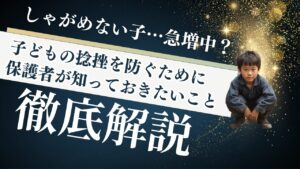
コメント